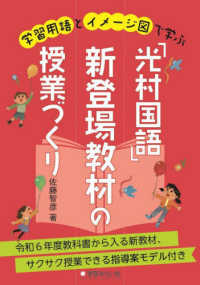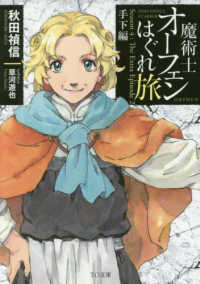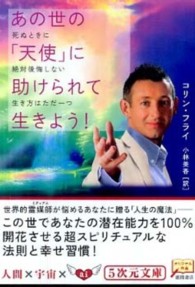内容説明
優しい口調のソネットに鋭いアイロニーをこめ25歳の若さで夭折した立原。彼の詩世界と新古今集の独自な関わりを解明。
目次
1 詩人の出発と比較文学
2 新古今への親炙
3 ソネット「またある夜に」と藤原定家
4 音楽の聴こえる詩、ドイツ語の響き
5 言葉で描く絵、本歌取りの詩学
6 物語の世界へ
7 危機に花を求めて
8 さまよいと住みか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ダイキ
4
リルケやシュトルム、定家が読みたくなった。堀辰雄は立原に「本を読むより恋をしろ」と助言していたらしい。全くその通りだと思う。「立原道造の抽象的な詩的世界は、一見現実から逃避したと見えて、実は、現実との絶えまない闘いを通して確保され、あやうい均衡の上に花開いていたのである。いわゆる四季派的な自然の肯定も出来ず、日本浪曼派的な観念を信じることも出来なかった立原の言葉は、音楽に接近してやまないその極度の貧しさ、言い換えれば純粋さゆえに、かえって時代の不毛に対して最大限の抵抗をする強靭さを持ったのであった。」2016/10/21
nightU。U*)。o○O
0
道造が愛読した定家との関係を、そしてそこからの発展、若く伸び白のふんだんに残されていた道造の詩的成長を綿密に探った研究報告。この時代の詩人たちに思われるそれぞれのふるさと、という問題で、彼の場合「自分の詩のうちにしかなかった」と導き出したのは見事。そして新古今とも通じる箇所、人工的――要は自分で作り出す、という気概に関心した。それにしても彼のソネットはそんな熱いところが出ていなくて凄い。2014/01/20