内容説明
平安前期に生まれ、室町時代の隆盛から江戸に至り、俳諧にも大きな影響を及ぼした連歌。五七五と七七を別人が詠む「つける」行為はどのように行われたか。文芸形態および言語遊戯としての側面にあらゆる角度から光をあて、連歌の本質的かつ根源的なたのしみと、連歌にのめり込んだ人々の熱気を知る。
目次
第1話 つける―連歌という文芸
第2話 うつろう―変化の妙
第3話 本歌をとる―和歌との交響
第4話 とりなす―転換の技
第5話 つくる―裏技を少々
第6話 つかず―うまくいかない時もある
著者等紹介
鈴木元[スズキハジメ]
1963年1月愛知県に生まれる。1985年3月愛知県立大学文学部国文学科卒業。1997年3月中京大学大学院博士後期課程修了。専攻、日本中世文学。学位、博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
168
「つける」行為の本質を問いながら実作を味わう本。百韻では、初折は落ち着いた句、二折で浮き立つ句、三四折でクライマックス…という変化を尊ぶ。句から句への「うつろひ」には季や去嫌(さりきらひ)など種々の規則を必要とした。宗匠は百韻の流れを導きつつ、形式的な瑣末主義に陥らぬよう時に応じて融通無碍の裁量を揮った。本書では「とりなし」という技法や本歌取りとの関わりを紹介する一方、巧く「つかなかった」場合もあげている。中々付かぬ悩みと付けおおせた喜びが沙石集に書かれており、傑作に辿り着くまでの苦心と楽しみがわかった。2024/10/12
良さん
3
連歌をつくる時のポイントが「つける・うつろう・本歌をとる・とりなす・つくる・つかず」という6つの動詞でコンパクトに取りまとめられている。読み物としても面白いし、学術研究の着実さも感じさせる好著。 【心に残った言葉】遊びがそのまま芸術たるわけではない。だが、連歌を材として繰り広げられた狂騒を、芸術的洗練を極めんとする『新古今集』編纂の裏面史のひとこまとしか見ないとすれば、その精神は貧困である。『新古今集』の編纂と平行してあった連歌会の喧噪は、必ずや後鳥羽院や定家をはじめとした当時の歌人たちの詩的精神に、燦然2013/01/02
山がち
2
単に付合いの妙であるならば俳諧でも構わないはずで、連歌と俳諧の違いをきちんと説明していないのは不十分と言わざるを得ない。しかし、それを差し引くならば、付けることに重点を置いて解説しており、それも歌論書を引いて式目に即しているあたり、良くできた一冊だと思った。さらに、狂言や日記などから様々な逸話を紹介してくれているのも大いに楽しめた。実際、連歌の煩雑さを思うと、これほどまでに様々な情報を切り捨てつつも、その雰囲気を楽しむことができたのは何よりである。初めて連歌に関して触れる一冊としても悪くはないようい思う。2013/05/24
紅独歩
1
連歌とは何かという問いに対して、正確に答えられる人は少ないのではないだろうか。その複雑なルールを分かりやすく(と言っても正確に答えられるかどうか自信はないが)、ユーモアを交えて解説した入門本。当時の人間関係、勢力図にまで話題がおよんでおり、門外漢でも楽しめる内容だ。それにしてもこの娯楽、浮世離れしすぎてやしないか。2012/11/05
-
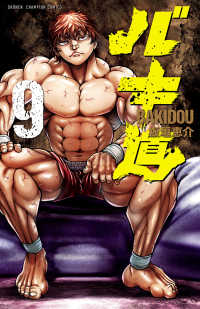
- 電子書籍
- バキ道 9 少年チャンピオン・コミックス
-
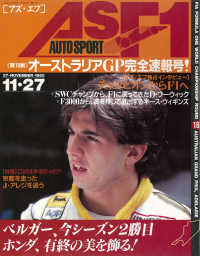
- 電子書籍
- AS+F(アズエフ)1992 Rd16…
-
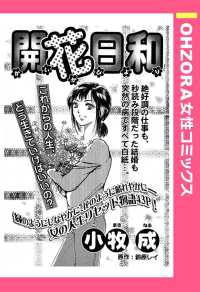
- 電子書籍
- 開花日和 【単話売】 - 本編 OHZ…
-
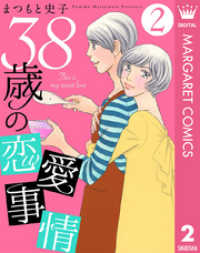
- 電子書籍
- 38歳の恋愛事情 2 マーガレットコミ…





