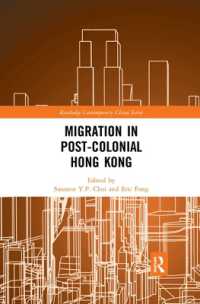内容説明
漢文学の藤原明衡と、かな文学の菅原孝標女。文化的な立場が大きく異なるふたりは、平安京という都市空間に時をほぼ同じくして生きていた。仏教的厭世観がただよう末法の世で、ふたりはそれぞれの文学にどんなしぐさやことばを書きつけたのか。思いがけない出会いは、現代のわたしたちにさえ、まだない未来への導きを提示する。
目次
1 無根拠への問い―末法到来
2 新・旧の党派対立のはざまで―藤原摂関体制VS後三条天皇
3 都市につどう人々―藤原明衡論(その一)
4 千年紀の社会学者―藤原明衡論(その二)
5 物語作家への道―『新猿楽記』VS『更級日記』
6 転機としての天喜三年―菅原孝標女論(その一)
7 すまじきものは宮仕え―菅原孝標女論(その二)
8 名前に拠り所を求めて―菅原孝標女論(その三)
はじまりはこれから―「ないもの」への想像力
著者等紹介
深沢徹[フカザワトオル]
1953年神奈川県相模原市に生まれる。立教大学大学院文学研究科日本文学専攻博士前期課程修了。専攻・学位:平安・院政期の文学(文学博士・立教大学)。現職:桃山学院大学社会学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。