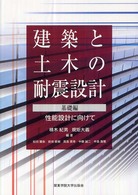出版社内容情報
《内容》 糖尿病患者の急増に伴い,非専門医も糖尿病患者を診る機会の多くなった現在,これから糖尿病を学ぼうとする研修医や家地医家のために明快に解説した入門書. 《目次》 第1章 糖尿病臨床の特色 A.共通の理念に基づいた個別性 B.十分な説明と本人の納得 C.治療開始時の説明 D.長期予後を視野に入れた疾患管理/バトンタッチの思想 E.患者を指導するのでなく援助する視点 F.チーム医療と主治医の関係──糖尿病専門医とかかりつけ医のバランス 第2章 糖尿病の診断と評価 A.糖尿病の疾患概念 B.糖尿病があるか否かについての診断 1.どのような患者で糖尿病の存在を疑うべきか a.無症状の場合 b.糖尿病を疑う自覚症状 2.糖尿病があるか否かを判断する具体的な手順 C.糖尿病患者での病歴採取上の注意点 1.主 訴 a.高血糖の自覚症状 b.合併症による自覚症状 2.現病歴 a.流れを視野にいれた病歴 3.家族歴 4.既往歴 a.体重の変遷 b.生活習慣 c.血圧,脂質代謝異常 d.薬剤歴 5.特殊型 D.身体所見上での注意点 1.糖尿病全般について a.角膜 b.脈 c.血圧 d.口腔内 e.甲状腺腫/皮膚の湿潤/頻脈/手指振戦 f.腹部 g.下肢 2.2次性糖尿病 E.糖尿病の病型診断 1.病型診断の実際 a.自己免疫の指標 b.β細胞機能 c.特殊型の診断 d.筆者らの提唱する糖尿病の病型分類 F.糖尿病の臨床病期分類 ─重症度の判断 1.標準的な病期分類 2.筆者らの考える糖尿病の病期分類(G-C分類) a.高血糖(代謝失調)の程度からみた分類─G分類 b.糖尿病性合併症の程度からみた分類─C分類 c.総合判断 G.糖尿病の評価に必要な検査 1.血糖値 a.食後(随時)血糖 b.空腹時血糖 c.血糖の日内変動 d.HbA1c e.1,5アンヒドログルチトール f.その他の血糖コントロールの指標 g.尿糖 h.筆者が日常行っている実際的なアプローチ 2.インスリン分泌能 a.75g OGTT b.尿中CPR 3.インスリン抵抗性 4.自己抗体 a.抗GAD抗体 b.インスリン自己抗体 c.抗IA2抗体 5.HLA H.糖尿病患者の入院適応 I.社会医学的な見地からの評価 第3章 糖尿病性急性代謝失調の診断と治療 A.診 断 1.急性代謝失調を疑うべき状態 2.急性代謝失調の鑑別点 a.臨床検査 b.併発している糖尿病以外の疾患 B.治 療 1.輸液の選択 2.輸液量 3.インスリン 4.ある程度血糖が下がったら 5.電解質の補正 6.NKHCの治療 C.急性代謝失調に準ずる状態 第4章 慢性期の糖尿病の治療 A.血糖コントロール 1.治療計画の立案 a.血糖コントロール目標の設定 2.血糖コントロールの速度について 3.血糖自己測定(self-monitoring of blood glucose:SMBG) B.非薬物療法 1.食事療法 a.食事療法の意義 b.食事療法の実際 c.糖尿病で食べていけないものがあるか d.食塩と脂質 2.運動療法 a.運動療法の意義 b.運動療法の実際 c.運動の禁忌 C.薬物療法 1.経口血糖降下剤 a.インスリン分泌促進剤 b.インスリン抵抗性改善剤 c.その他 d.異なった種類の経口剤の併用 e.糖尿病治療剤の副作用 f.経口血糖降下剤使用の実際 2.インスリン a.インスリン注射の考え方 b.インスリン注射の適応 c.インスリンの種類と使用法 d.インスリン注射の実際 e.インスリンと経口剤の併用 第5章 合併症の診断と治療 A.ミクロアンギオパチー 1.眼 症 a.糖尿病性網膜症と白内障 b.治療 2.腎 症 a.臨床診断 b.自覚症状 c.腎症の評価 d.腎生検 e.治療 3.神経症 a.診断 b.治療 4.壊 疽 B.マクロアンギオパチー 1.自覚症状 2.身体所見 3.検査所見 4.治 療 第6章 境界型高血糖 A.病 態 B.臨床的な問題点 1.糖尿病への移行 2.糖尿病への移行以外の問題点 第7章 高血圧と脂質代謝異常 A.高血圧 1.2次性高血圧を疑うべき徴候 a.クッシング症候群 b.褐色細胞腫 c.アルドステロン症と腎血管性高血圧症 d.末端巨大症 2.治 療 a.降圧の目標値 b.非薬物療法 c.薬物療法 B.脂質代謝異常 1.インスリンの脂肪代謝への作用 2.著しいインスリン欠乏状態での脂質代謝異常 3.2型糖尿病での脂質代謝異常 4.脂質代謝異常の診断と治療 a.脂質代謝異常の評価 b.治療 第8章 特殊な問題 A.外科手術 B.妊娠 C.感染症 D.暁現象とソモジー現象 E.シックデイ 第9章 低血糖 A.低血糖と考えるべき血糖値 B.自覚症状 C.メカニズム D.低血糖の診断と治療 1.診 断 2.治 療 a.当面の処置 b.低血糖の原因解明/低血糖の予防 第10章 糖尿病の発症メカニズムとブドウ糖毒性 A.糖尿病の発症メカニズム 1.ブドウ糖の流れ とその調節因子としてのインスリン a.臓器レベルでの糖の流れ b.細胞内でのブドウ糖の流れとインスリンによるその調節 2.マクロ的な糖尿病の発症原因 3.インスリン不足とインスリン抵抗性 a.インスリン不足 b.インスリン抵抗性 B.ブドウ糖毒性 1.ブドウ糖毒性が生ずる可能性のある血糖レベル 2.ブドウ糖毒性のメカニズム 3.ブドウ糖毒性と糖尿病臨床 第11章 将来への期待 A.糖代謝異常の早期診断と早期介入 1.境界型への介入 2.糖尿病発症初期の介入 B.新たな治療手段の開発 1.薬 剤 2.食事療法 C.新たな機器 1.非観血的血糖モニター D.遺伝子
内容説明
本書は臨床糖尿病学への入門書である。読者としては、主として糖尿病臨床の現場でこれから糖尿病について勉強してゆこうとする研修医や一般内科医の方々を意識している。そして本書は、いわゆる教科書的な順を踏んだ構成でなく、著者自身がこれまで糖尿病の専門医を目指して勉強してきた過程をなぞるような構成となっている。
目次
第1章 糖尿病臨床の特色
第2章 糖尿病の診断と評価
第3章 糖尿病性急性代謝失調の診断と治療
第4章 慢性期の糖尿病の治療
第5章 合併症の診断と治療
第6章 境界型高血糖
第7章 高血圧と脂質代謝異常
第8章 特殊な問題
第9章 低血糖
第10章 糖尿病の発症メカニズムとブドウ糖毒性
第11章 将来への期待
著者等紹介
相沢徹[アイザワトオル]
信州大学医学部老年医学助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 蒼穹の剣【タテヨミ】第34話 picc…
-

- 電子書籍
- RIGHT∞LIGHT4 夜天の頂へ、…