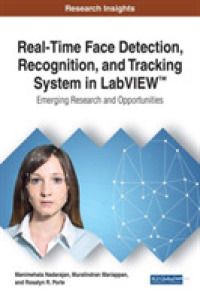出版社内容情報
運動が苦手で人見知りの蒼太郎と運動神経がよくてお調子者の律。対称的なふたりの中学1年生男子が、化学者の森井老人の指導のもと、人類がどうやって「青色」を手にしたのかを証明する壮大な実験に挑戦する。顔料に使えるような青色の石(鉱物)は自然にはほとんど存在しないため、古代から人類は様々な工夫をして「青」を作ってきた。銅やお酢、ウシの血など、簡単に手に入る材料から高価な青を作りだした、人類のあくなき探究の旅にあなたも同行しませんか?
内容説明
運動が苦手で人見知りの蒼太郎と運動神経がよくてお調子者の律。対称的なふたりの中学1年生男子が、化学者の森井老人の指導のもと、人類がどうやって「青色」を手にしたのかを証明する壮大な実験に挑戦します。顔料に使えるような青色の石(鉱物)は自然にはほとんど存在しません。だからこそ人類は古代からさまざまな工夫をして「青」を作ってきたのです。銅やお酢、ウシの血など、簡単に手に入る材料から高価な青を作りだした、人類のあくなき探究の旅にあなたも同行しませんか?
目次
第1章 ヴェルディグリとオドントライト
第2章 ラピスラズリとウルトラマリンブルー
第3章 スマルトとフォルスブルー
第4章 エジプシャンブルー
第5章 骨董店と科学倶楽部
第6章 マヤブルー
第7章 プルシアンブルー
第8章 埴輪
第9章 中世の青色の話
第10章 旅立ち
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
☆よいこ
83
児童書。YA。筑波大学の教授と油彩画の保存修復の専門家の共著。美術史を彩る「青色」の歴史をストーリーで辿る▽中学1年生の蒼太郎(そうたろう)と律(りつ)は、夏休み期間に科学倶楽部を主催する森井老人の助手をする。森井老人は元大学教授で、中央美術館の研究員に頼まれて、展示用の「青」の史料を再現する。蒼太郎と律は、鉱物を砕いたり牛の血液を煮たり臭い藻を採取したりして古代の「青色」をつくる▽錬金術。実験の楽しさがよく伝わる物語。巻頭にカラーで実物の写真がある。良本。2025.1刊 2025/03/27
たかこ
57
読友さんのレビューから。13歳からの考古学シリーズ本。中学生の時にこういった経験ができるのは豊かだと思う。単なる知識習得の勉強ではない、手を動かしたからこそわかる自然や化学の知識、そして一緒に活動する人との関わり。友達や家族、先生やそれ以外の大人等と一緒に行動したからこそ得られるものだと思う。そして、青の内容も面白かった。私の青色のおすすめは、金沢の前田家の奥方のために建てられた成巽閣(せいそんかく)、中でも群青の間のウルトラマリンブルーは必見。漫画では、『青の花器の森 小玉ユキ』波佐見焼きの呉須の青。2025/04/30
さつき
50
中学生の蒼太郎と律が科学倶楽部の先生のお手伝いで様々な青色を作る実験をする、という設定が楽しい。ウルトラマリンブルー、ヴェルディグリ、エジプシャンブルー…古代の人々がどれだけ苦労して青を作ったかがわかり何だか感動します。最初はわけもわからず先生に言われるままに作業していた2人が将来の夢を見つけていくストーリーも爽やか。13歳からの考古学というシリーズの一冊ですが他にも面白そうな作品がありこれから読んでいきたいと思います。2025/07/20
まる子
29
上野にある科学倶楽部に所属する中1の蒼太郎と律。化学者の森井老人に出会った事で、古くから人が求めていた「青色」を知る実験へ。古代、ラピスラズリの鉱物から作られる天然のウルトラマリンブルー1グラムは、金1グラムと同じ価値だった事に驚き、その青を手に入れるには手のかかる作業だった。古墳時代の日本では青を作るために酸化させる技法で青や緑を作っていたそう。古代エジプトで使用された「青色」の原料ラピスラズリはアフガニスタンで採取される鉱物だった。13歳からの考古学シリーズ。個人的には「ファラオ」より好き。2025/02/17
今庄和恵@マチカドホケン室コネクトロン
17
13歳からの考古学とあるように、主人公は中学生。夏休みに理科実験教室で「青」色作りを手伝ったことにまつわる物語。海と空が青いせいか自然界に青は豊富にあるものと勘違いしてましたよ。希少な青は特別な意味を持たされ、錬金術と同じレベルで人為的に作り出すことを人に目指させた。青色の化学的歴史的な解説は「へえ〜!」の連続。美術展がどのように作り上げられていくかということを垣間見ることができました。中学生の仲良しコンビが青色作りをきっかけに進む道を見つけていく、意外な胸熱物語。2025/12/11
-
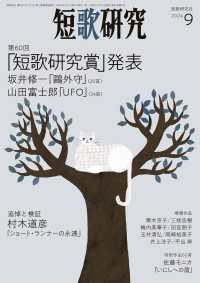
- 電子書籍
- 短歌研究2024年9月号