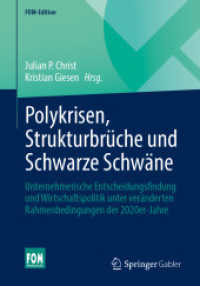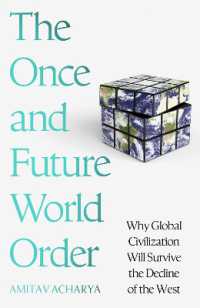出版社内容情報
土器を赤く塗り、棺に朱を敷きつめ、魏志倭人伝に「朱丹を以てその身体に塗る」と記された弥生人。その朱の原料、辰砂を採掘していた痕跡が徳島県阿南市ではじめてみつかった。山中の発掘調査から、鉱脈を追いかけ岩盤を切り崩す採掘の実態を明らかにする。
内容説明
土器を赤く塗り、棺に朱を敷きつめ、魏志倭人伝に「朱丹を以てその身体に塗る」と記された弥生人。その朱の原料、辰砂を採掘していた痕跡が徳島県阿南市ではじめてみつかった。山中の発掘調査から、鉱脈を追いかけ岩盤を切り崩す採掘の実態を明らかにする。
目次
第1章 弥生人が求めた朱(辰砂採掘遺跡とは;弥生の赤 ほか)
第2章 辰砂採掘遺跡の探究(採掘場への道のり;辰砂採掘遺跡の発見 ほか)
第3章 採掘の実態解明へ(ズリ場と鉱脈の発見;みえてきた露天採掘の実態 ほか)
第4章 朱の生産にせまる(辰砂はどこへ;朱をつくる弥生人;朱塗り工房の風景)
第5章 若杉山辰砂採掘遺跡のこれから
著者等紹介
西本和哉[ニシモトカズヤ]
1982年、兵庫県姫路市生まれ。奈良大学文化財史料学博士後期課程単位取得退学。2009年、徳島県教育委員会入庁。現在、公益財団法人徳島県埋蔵文化財センター主任研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月をみるもの
14
自然と人間の関わりにおいて、農業はどうしても人間の都合のよいように自然を改変する、、というイメージがつきまとう。それに対して鉱業は(1)自然の恵みたる鉱物を人間が見つけ出し(2)採掘することで自分の手元にとってきて(3)さらに選鉱し抽出処理をする という多段階のステップによって、自然を少しずつ人間の側に引き寄せる活動という感じがする。しかも辰砂は、石炭のように燃やせるわけでもなければ、黒曜石のように刃物として実用になるわけでもない。葬送儀式などに用いられる純粋な「第二の道具」だ → つづく 2023/08/30