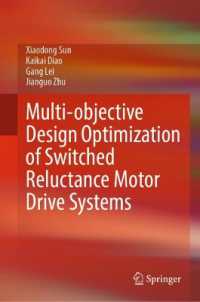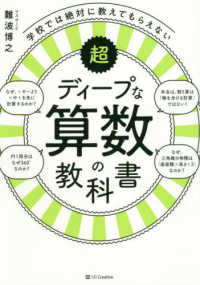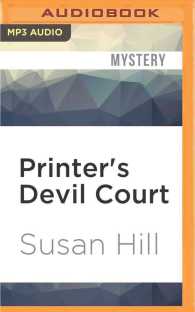出版社内容情報
装飾品である貝輪は、そのかたち・色・艶・質感から古来より多くの人々を魅了してきた。本書は、とくにオオツタノハ製貝輪に着目し、縄文時代から弥生・古墳時代にかけての人々と貝との関わりについて、貝塚や墓などから出土した遺物と現在の生息状況の調査結果から論じる。装飾品に使われた貝を調べることで、当時の習俗・交易ルート・社会形態などさまざまな事柄がみえてくる。
目次
第1章 食用の貝と利器用の貝
第2章 東日本における縄文時代の貝輪
第3章 東日本における弥生時代の貝輪
第4章 東日本におけるオオツタノハ製貝輪
第5章 九州地方における縄文時代の貝輪
第6章 南西諸島におけるオオツタノハ製貝輪
第7章 考古学・生物学的調査が明かすオオツタノハ製貝輪の実態
著者等紹介
忍澤成視[オシザワナルミ]
1962年千葉県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科史学・考古学専攻修士課程修了、博士(文学)。市原市教育委員会文化財課チバニアン整備推進係副主査(再任用)(2024年4月より)。千葉市教育委員会埋蔵文化財調査センター主任研究員、東京大学大気海洋研究所特任研究員、早稲田大学文学学術院非常勤講師。日本考古学、おもに生物学的視点から貝を素材とした装飾品類を研究。縄文から古墳時代まで続く「日本列島最長の威信財」とされるオオツタノハ製貝輪(腕輪)の謎を解明するため、列島各所の島嶼部を20年以上にわたって単独調査。2021年、第46回「藤森栄一賞」受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。