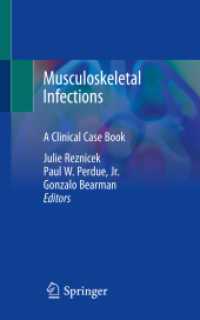出版社内容情報
〈エネルギーのあり方を問い直し、これからの社会のあり方を考える。〉
近代以降の燃料革命はエネルギーの由来を不可視化し、消費地と供給地の関係に圧倒的な不均衡をもたらし、農山村の社会と自然環境を疲弊させてきた。
巨大開発に直面した地域の過去・現在・未来を見つめ、公正なエネルギーへの転換を構想する。
〈本書が、望ましいエネルギー転換のあり方を問うにあたってまず行ったのが、私たちのエネルギー利用が誰のどのような犠牲の上に成り立つものであったのかを直視し直すことであった。そして、犠牲を強いられがちな人びとがエネルギー資源や施設といかに向き合ってきたのかについて、歴史をさかのぼりながらとらえ直す作業であった。
誰の健康も生活も犠牲にせずエネルギーを生み出すことは容易ではない。だからこそ、「公正なエネルギー」への転換は、世代内と世代間の双方において「公正な社会」への転換を要請する。--編者〉
【執筆者】山本信次/中澤秀雄/浜本篤史/山室敦嗣/西城戸 誠/古屋将太/本巣芽美/丸山康司/石山徳子/立石裕二/寺林暁良
内容説明
エネルギーのあり方を問い直し、これからの社会のあり方を考える。近代以降の燃料革命はエネルギーの由来を不可視化し、消費地と供給地の関係に圧倒的な不均衡をもたらし、農山村の社会と自然環境を疲弊させてきた。巨大開発に直面した地域の過去・現在・未来を見つめ、公正なエネルギーへの転換を構想する。
目次
序章 環境社会学の視点からどのようにエネルギー問題をとらえることができるのか
1 エネルギーの近代化と地域社会の変貌―「中央」と「地方」(薪炭利用の変遷とエネルギーの由来の不可視化―農山村と都市の関係の変容;石炭産業の盛衰と地域社会―さわれる資源としての石炭;大規模ダム開発と地域社会―庄川流域における水力発電事業と住民の摩擦を中心として)
2 原子力の台頭と地域社会の葛藤―生活の場からの問いかけ(「原子力半島」はいかにして形成されたか―下北半島・六ヶ所村の地域開発史と現在;原子力施設の立地点における生活の場の再創造―茨城県東海村の事例から;原発に抗う人びと―芦浜原発反対運動にみる住民の闘いと市民の支援)
3 これからのエネルギー転換と地域社会―世代内・世代間の公正の実現(反・脱原発の市民運動によるオルタナティブの創出―生活クラブ生協の実践を事例として;地域分散型再生可能エネルギーの進展とその障壁;地域社会から見た風力発電事業の課題と社会的受容―地域と風力発電の共生に向けて;エネルギー転換を可能にする社会イノベーション)
終章 これからのエネルギー転換に向けて―公正でタンジブルなエネルギーをつくり、使っていくために