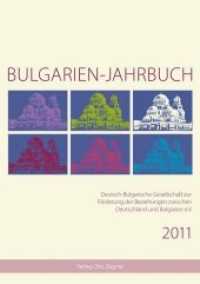出版社内容情報
角田 徳幸[カクダノリユキ]
著・文・その他
内容説明
日本の鉄は、明治時代初期まで九割以上が中国地方で生産されていた。神秘的な鉄づくり、日本刀の材料となる玉鋼づくりという、たたらの画一的なイメージを超えるその実像を発掘調査と操業当時の記録から明らかにしていく。
目次
第1章 金属学者たたらを歩く
第2章 砂鉄の採取―砥波上鉄穴
第3章 中国山地のたたら―都合山鈩・砥波鈩
第4章 山陰沿岸部のたたら―価谷鈩
第5章 たたらの実像
第6章 たたらを活かした地域づくり
著者等紹介
角田徳幸[カクダノリユキ]
1962年広島県生まれ。島根大学文学専攻科修了。博士(文学)。島根県教育庁文化財課、島根県立古代出雲歴史博物館、島根県埋蔵文化財調査センターなどをへて、現在、島根県古代文化センター長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ステビア
15
流し読み2024/11/19
はじめさん
12
もののけ姫でイメージしやすい、山陰のたたら製鉄遺跡について学ぶ。我が国では鉄鉱石採れないので、砂鉄から精錬する技術として、たたらが用いられた。炉を覗いて片目、ふいごを踏んで片足が潰れた山の神・一本ダタラの原型云々は民俗学でも広く知られた概念ですね。トンデモなら大陸のタタール族から製鉄技術伝来でたたらとかね。貴重な白黒写真で、土砂を取る場所に当たりをつけたりする職能へのスポットや、現代に残る遺跡から製鉄の過程を解説。炉を燃やすために山林から伐採。杉の巨人フンババを斃した中東のギルガメッシュも文明=鉄の力を?2023/04/13
tnk
0
たたら関係書は「鉧」「銑」など難解な用語が頻出するが、この本は初歩から説明してくれる。もののけ姫に描かれるイメージ、日本刀との関係はたたらの一面に過ぎないことが分かる。2024/08/06