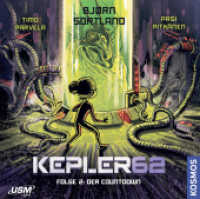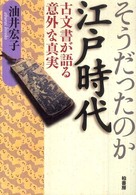内容説明
秋山理乃は歴史が大好きな中学1年生。高校の世界史の先生だったキシローじいちゃんと東京で開かれた「ラスコー展」に行って、謎深い洞窟壁画の魅力にすっかりはまってしまう。そして、キシローじいちゃんの教え子で、洞窟壁画の研究者のタバタさんの案内で、フランスに本物の洞窟壁画を見に行くことに。旧石器時代の壁画を見た理乃は、なんで大昔の人はわざわざ真っ暗な洞窟に壁画を描いたのか、という疑問で頭の中がいっぱいになる。帰国後も、タバタさんとじいちゃんの協力のもと、文化祭で発表する「美術のはじまり」というテーマの答えを求めて、理乃の奔走は続く…。
目次
プロローグ はじめての文化祭を終えて
第1章 洞窟壁画って何?
第2章 春休みのフランス旅行1―ボルドーとヴェゼール渓谷
第3章 春休みのフランス旅行2―レゼジーとパリ
第4章 動物と人間の違いって何?
第5章 文化祭に向けてのアイディアをまとめる
エピローグ―10年後の野外調査
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
82
13歳の理乃が元歴史教師の祖父と洞窟壁画の研究者タバタさんの案内で、フランスのラスコー4やヴェゼール渓谷の先史的景観と装飾洞窟群の世界遺産を訪れ、何のために洞窟壁画を描いたのか、そもそも人間が美術を制作するのはなぜかという疑問に突き当たる。パリの人類博物館、茅野市の尖石縄文考古館も訪れ、旧石器時代のヴィーナス像の世界的共通性なども絡めて、人間にとって視覚シンボル・象徴とは人間が社会的生き物であり、コミュニケーションの役割も大きかったという指摘は、考古学、美術、行動生態学に及ぶ重要な観点で深い読み物である。2021/02/20
☆よいこ
78
中学1年の秋山理乃(あきやまりの)は歴史部の発表テーマに悩んでいた。高校世界史の元教師の祖父と一緒に「ラスコー展」を見て洞窟壁画に興味を持つ。専門家のタバタさんに話を聞き、春休みにフランスに行く。実際に洞窟壁画やルーブル博物館を訪ねて、文化祭の発表をまとめていく。▽巻頭にカラーで動物壁画の写真や解説、洞窟周辺の地図などが詳しくあり分かりやすい。物語になっているので、読むだけでなんかわかる。調べたことをメモし、分類し、まとめていく作業がわかる。2021年刊。良本2022/09/28
さつき
54
中1の理乃は元高校教師の祖父の影響で歴史好き。上野で見たラスコー展をきっかけに洞窟壁画を見にフランスに!歴史好きな少女が自分の興味のあることに一生懸命に向き合う姿は見ていて清々しいです。洞窟壁画についてはほぼ知らない事ばかりで、私も理乃と一緒に探求の旅を楽しみました。2025/10/12
kuukazoo
14
10代向けのノベル仕立ての本だが、ラスコー及び周辺の洞窟壁画について詳しく解説されており勉強になった。中1の歴史好きの少女が展覧会でラスコーの壁画を知ったのをきっかけに、旧石器時代の人々が洞窟の壁に動物たちの絵を描いた理由や美術という行為の意味について、元世界史教師の祖父や教え子の研究者たちの助けを得ながら自分なりの答えを見つけようとする。美術はコミュニケーションの手段、というのは興味深い。2024/12/31
くみ
10
ラスコー洞窟の壁画は社会科でちらりと習いましたが、その絵から受けたインパクトがまだ印象に残っています。何を伝えたくて描いたのかな、そもそも本当にそんな昔に人間がいたんだとか、感動します。文字の記録がない分、人間は描いてないとか、用途不明の模様が書かれているとか、その現象から色々推察できます。学ぶことは考えることだと思うので、その楽しさを味わうことができました。そして、ストーリー上とはいえ、渡仏して本物も見学するなんて!羨ましい!2026/02/01