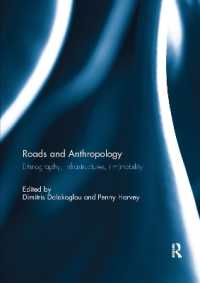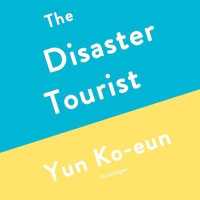内容説明
制度疲労により、劣化しつつある地域社会を必死に支える「しんがり」たちの奮闘と、学生や市民と意見を交わした講座の様子をまとめました。全労済協会の大学寄附講座から地域の困窮と闘う11人のしんがりを紹介。
目次
序文 社会のしんがり―しんがりに学ぶ地域の困窮との闘いかた
第1部 子どもを取り巻く問題(子ども・若者の貧困と地域の居場所づくり;逆境から自立する子どもにチャンスを―児童養護施設から自立する子どもが直面する課題)
第2部 貧困・社会的孤立の問題(生活困窮者への伴走型支援のかたちを探る;ひきこもり等で孤立する子ども・若者をアウトリーチで支援する)
第3部 障害者問題(発達障害の人の困りごとを解決することはユニバーサル社会の第一歩;ダイバーシティ社会・障害者雇用支援;障害者雇用の新潮流)
第4部 地域社会の取り組み(生活保障の再構築と全員参加社会の構築―自ら選択する福祉社会;制度のはざまから社会福祉を見直す;生活困窮者と家計相談支援―野洲市が取り組む相談支援;個人でできる社会から江戸時代の社会へ 共生社会の実現へ向けて―地方都市の生き残りをかけた挑戦)
おわりに―コウテイペンギンの子育ての寓話
著者等紹介
駒村康平[コマムラコウヘイ]
慶應義塾大学経済学部教授、ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター長。1964年生まれ。慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。博士(経済学)。国立社会保障・人口問題研究所、駿河台大学経済学部助教授、東洋大学経済学部教授などを経て、2007年から慶應義塾大学経済学部教授。厚生労働省顧問、社会保障審議会委員(年金部会、年金数理部会、生活保護基準部会部会長、障害者部会部会長、生活困窮者自立支援及び生活保護部会部会長代理、人口部会)、金融庁金融審議会市場WG委員、社会保障制度改革国民会議委員など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sayan
nekosogi
takao
Junk