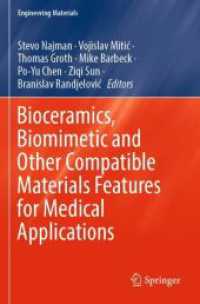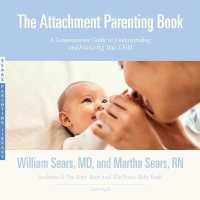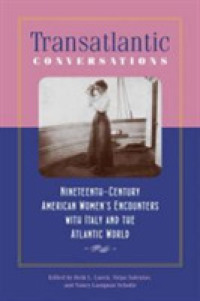内容説明
近代社会を自己言及的な「全体社会システム」とするルーマンの「社会」および「近代性」に関する論考は、従来行われてきた社会に関する諸説の中枢に据えられてきた概念や定式に変更をもたらす。進化、階級、科学、合理性、そして理念史。社会学的パースペクティヴにおける理念の歴史。
目次
第1章 意味、自己言及、そして社会文化的進化
第2章 社会階級の概念について
第3章 科学の発生―認識獲得システムの分出
第4章 近代社会の合理性
第5章 社会学的パースペクティヴにおける理念史
著者等紹介
ルーマン,ニクラス[ルーマン,ニクラス] [Luhmann,Niklas]
1927年生まれ。1968~1993年ビーレフェルト大学社会学部教授。1998年没。二〇世紀を代表する社会学者の一人。哲学者ハーバーマスとの論争を経て一躍その名を広め、現象学、ポスト構造主義などを射程に収めた、独自の社会システム理論を展開。法、経済、政治、科学、宗教、芸術、教育など、社会における諸機能システムや、社会におけるゼマンティクの研究、エコロジー、リスクなど、現代社会の固有なテーマに言及した著作を多く著す
土方透[ヒジカタトオル]
1956年生まれ。聖学院大学教授。中央大学大学院文学研究科博士課程修了、社会学博士。ハノーファー哲学研究所、ヴュルツブルク大学、デュッセルドルフ大学などにて、客員教授を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぷほは
1
『社会構造とゼマンティク』や『情熱としての愛』などと同様、知識社会学系の論文が5篇収録されている。中でも2章の「階級」概念を主題としたものが一番興味深く、また訳も読みやすく、これだけでも読んだ価値はあった。他の章で言えば1章の「進化」概念に関して「計画」概念との差異から切り込んでいくあたりは流石の強力さなのだが、他は訳がもうひとつなのと、ルーマン本人が何を言ってるのか分からないのと相まってなかなか手ごわかった。気になるのは自己言及を中心に編まれた論集ではあるのだが、それにしては自己論理への言及がないこと。2017/08/09