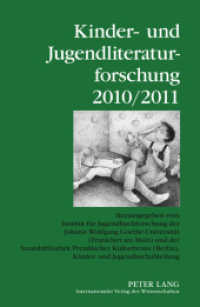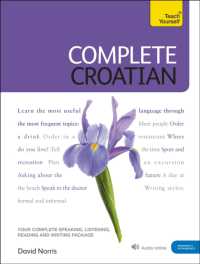内容説明
大発見以来、卑弥呼の住んだ宮都かと話題になってきた吉野ヶ里遺跡。一時期の喧噪が終息したいま、あらためて集落の成立から拡大、終焉までの展開をくわしく追究し、「倭人伝」記事との対照、中国城郭の影響などの検討をとおして、邪馬台国時代のクニの都であると論じる。
目次
第1章 吉野ヶ里遺跡の発掘(吉野ヶ里遺跡とは何か;吉野ヶ里研究の先人・七田忠志;ベールを脱いだ大遺跡)
第2章 はじまりの集落(草分け的集団の集落;環壕集落の形成)
第3章 佐賀平野の中核集落へ(二〇ヘクタール超の環壕集落;青銅器生産工房;甕棺墓列とその埋葬者;墳丘墓と首長層)
第4章 クニの大規模集落へ(四〇ヘクタール超の大規模環壕集落;南内郭は有力者の居住域か;北内郭は祭祀空間か;高床倉庫群は交易の場か;墳墓と祭祀;豊富な出土品が語るもの)
第5章 吉野ヶ里遺跡と邪馬台国(倭人伝と吉野ヶ里のクニ;中国文化の影響;巨大環壕集落の終焉;よみがえる吉野ヶ里)
著者等紹介
七田忠昭[シチダタダアキ]
1952年、佐賀県神埼市神埼町生まれ。國學院大學文学部史学科(考古学専攻)卒業。1977年、佐賀県教育庁入庁、文化財保護事務と県内遺跡の発掘調査を担当し、1986年~2008年の22年間、吉野ヶ里遺跡発掘調査の発掘責任者を務めながら国営吉野ヶ里歴史公園の整備事業に携わる。その後、佐賀県立博物館・美術館長を経て、現在、佐賀県立佐賀城本丸歴史館長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月をみるもの
16
三内丸山遺跡が縄文時代を象徴するように、吉野ヶ里は弥生時代を代表する超メジャー遺跡だと思っていた。しかし実際は、工業団地造成のために締め切りを切られた中で発掘されており、保存されるかどうかは綱渡りだった。というか、むしろメディアを利用して世論を誘導し知事に決断を迫ったというほうが本当みたい。よくもわるくも考古学の発展は、戦後の高度成長とともにあったのだと実感。2018/12/16
えひめみかん
0
小学校の頃に私を考古学ファンの沼に陥れた思い出の遺跡。あれから30年以上経って、ずいぶんと発掘も調査も進んだようで2023/11/25
-
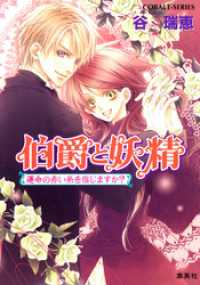
- 電子書籍
- 伯爵と妖精 運命の赤い糸を信じますか?…
-
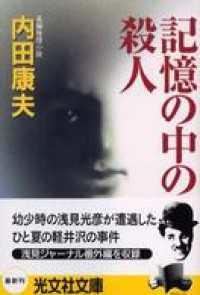
- 電子書籍
- 記憶の中の殺人 - 長編推理小説