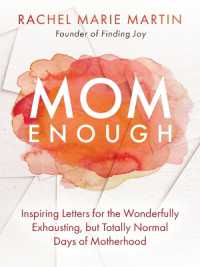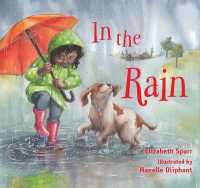内容説明
人口減少時代に掲げられた「一億総活躍社会の実現」という政策目標。労働力として注目をされ始めた女性たちの置かれた本当の姿とは?
目次
序章 一億総活躍のかげで―無業の女性たち
第1章 一隠総活躍時代の女性の状況
第2章 未婚無業の女性
第3章 大卒未婚無業の女性たちのそれぞれ
第4章 女子大生の夢と現実
第5章 既婚子持ち女性の再就職への壁
第6章 大卒無業女性と社会の未来
著者等紹介
前田正子[マエダマサコ]
甲南大学マネジメント創造学部教授。商学博士。早稲田大学教育学部卒業。公益財団法人松下政経塾を経て、米国ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院に子連れ留学。慶応大学大学院商学研究科後期博士課程修了。留学をきっかけに、ライフデザイン研究所(現:第一生命経済研究所)で女性の就労や子育て支援の研究を始める。2003年~2007年横浜市副市長。医療・福祉・教育担当。2007年~2010年公益財団法人横浜市国際交流協会理事長。2010年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
katoyann
24
関西の若年無業女性を事例として、正規雇用の職に就くために関西から首都圏へと人口が流出しているという実態を明らかにしている。私も関西の私大卒で、大学院を東京で過ごしたので、地域の感覚の違いは腑に落ちた。実は関西は性別役割分業意識が強く、女性には非正規職の募集が偏るため、首都圏に移動せざるを得ないという。エリアスタディというよりは、東京一極集中が起きる要素として古いジェンダー規範があると解く。巨大な文教地区を抱えている関西で、学歴に応じた雇用が不足しているというのは少し衝撃だった。2022/10/10
mazda
24
横浜市役所に勤務し関西の大学で教べんをとるようになった筆者が、「結婚したらどうせ仕事をやめるのに、なぜがんばるのか意味がわからない」という関西の女子学生の意識の低さに驚いたようです。学生だけではなく、ボーイフレンドが将来女性と一緒に働いて生計をたてようと言うと「そんな甲斐性のない男とはつきあうな」と言って別れさせたり、朝は会社の掃除をするように言うと「うちの孫にそんなかわいそうなことをさせるのか」とクレームをつける親、祖父母の存在も問題です。ツインターボじゃないとやっていけないですよ、今の世の中は…。2017/11/26
ず〜みん
10
私は音大に行きたかったのを「そんなのでメシは食えない」と猛反対されたクチで、働かないことはあり得ない、と育てられてきたけど、大卒で家事手伝い、という身分の人が実際いて、その周縁の問題や現状という未知の領域を知ることができたことが大きい一冊だった。2020/03/20
Mc6ρ助
5
『実はかって、1980年代には日本の経済成長のカギは「日本型福祉」にあるとして、「専業主婦は日本の福祉の含み資産」とまでいわれていた。日本の税や社会保険料が安いのは、専業主婦が育児も介護もすべて無償で担ってくれるから、というわけだった。それから40年近くたって、女性に期待されるものがより大きく、そしてより都合よく変わってきていることがわかるだろう。(p23)』専業主婦に甘えて構築した社会制度が40年近くたっても変わらない。さらに、介護保険などは社会が負担できないと家庭に負担を求めた・・・。誰に都合よいの?2017/09/17
ががが
4
政府が掲げる女性の社会進出とは裏腹の「大卒無業女性」に焦点を当てた本。当事者のヒアリングした内容も収録されており、今まで統計からは見えていなかった実態は興味深く読んだ。そもそも働かない女性が一定いることや期待される女性の社会的役割に地域差があることなど、見過ごされてきた論点が多い。人手不足が進む業界がある一方で、都市部にしか望む職がない現状、機能してない大学のキャリア教育に旧来の根強い家庭観と山積する問題には思わず溜息が出る。社会全体としては確かに人材を浪費しているが、個人にとってはどうなのかが気になった2023/05/03