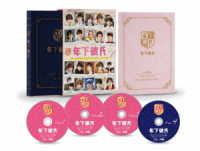内容説明
平泉を語るうえで「北」と「つわもの(武士)」という言葉は欠かせない。平泉藤原氏は中央の貴族社会に入っていかず、北東北の入り口にあたる平泉に館を築き、中世都市をつくりあげた。ここは北のつわものたちの集大成、京都とは異なる北の都だったのである。
目次
第1章 つわものたちの北東北
第2章 柳之御所遺跡の発見
第3章 都市・平泉のはじまり
第4章 拡大するつわものの都
第5章 平泉の最盛期
第6章 北の都の終焉と継承
著者等紹介
八重樫忠郎[ヤエガシタダオ]
1961年、岩手県生まれ。駒澤大学文学部歴史学科卒業。平泉町教育委員会文化財センター文化財調査員、世界遺産推進室室長補佐などを経て、現在、総務企画課課長補佐(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
天茶
2
★★★★★ 平泉の考古学的成果を知るならこれ! 膨大な、しかも日進月歩な平泉の考古学的成果をよくぞここまでコンパクトにまとめあげたものだと思う。しかも読みやすい。また考古学で分かるのはどこにどういう建物があっただけではなく、それを通じて当時の社会そのものに迫ることができるのだと分かる一冊。 2019/11/20
mk
2
考古学分野における平泉研究の最前線を切り開いてきた著者による遺構紹介の書。現時点における最新の発掘調査報告として、都市平泉に関する研究成果をわかりやすくコンパクトに解きほぐしてくれる。昭和末(1988)の柳之御所遺跡の発見以来、連綿として四半世紀にも及ぶ考古学的発見の数々が出土遺物の豊富な図版で紹介されるとともに、奥州藤原氏三代に及ぶ各時代の遺構が面的に検証され、北海道や北東北など関連遺跡とのつながりにも目配りが効いた良質な一冊に仕上がっている。全章を通じて、文化遺産としての平泉の巨大さが実感できる。2017/06/24
えひめみかん
0
来訪は10年くらい前。平面図も興味深いが、人の目の高さで現地見るのも一興。2017/01/04