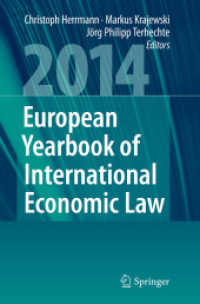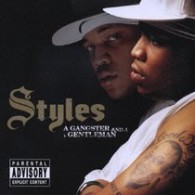内容説明
今はすっかり市街地となっている京都大学周辺の左京地区。かつてここには、扇状地上に豊かな森が広がっていた。この地に暮らした縄文人の行動と生活を追いつつ、東日本のように大きな環状集落をつくらず小さな暮らし方をした京都盆地の縄文世界を明らかにする。
目次
第1章 京都の市街地に縄文遺跡が(比叡山西南麓の扇状地;遺跡を群としてとらえる)
第2章 続々みつかる縄文遺跡(北白川追分町遺跡の発見;北白川小倉町遺跡の調査;編年研究から文化の研究)
第3章 縄文集落の移り変わり(人の活動がはじまる―縄文草創期・早期;扇状地の集落―縄文前期・中期;集落の拡大と衰退―縄文後期・晩期)
第4章 低湿地の森から(埋没林が保存されていた;先史環境の復元;貯蔵穴と木材加工場)
第5章 京都盆地の縄文世界(重層的な地域集団;小さな暮らし方)
著者等紹介
千葉豊[チバユタカ]
1960年愛知県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程中退。現在、京都大学文化財総合研究センター助教(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たか
6
前回はこのシリーズの大森貝塚を読んだから今回は京都。2016/05/19
chang_ume
3
比叡山西南麓に広がる北白川遺跡群、複合扇状地上の縄文早期〜弥生前期末。遺跡の消長を「群」の中の拠点移動と捉える視点は、ランドスケープ考古学に近づくものでした。集団の小規模性と長期継続性が、近畿地方の縄文世界の特徴として挙げられています。扇状地上の網状流路と微高地そして扇端湿地の先史環境、それらが弥生前期末のカタストロフィ的な大規模自然災害(土石流)によって埋没するまで。一方で、北白川遺跡群を東西日本の結節点と見なしつつ、土器動態の社会的条件を重視する立場は縄文研究の香りだなあと。2017/12/02
あむけ
1
数個の集落が鴨川付近に集中して、長期間にわたり住んでいたことが遺跡がかわらかるらしい。石器を製作したり、集落の有り様の変化も浮かび上がっているとのこと。身近な街の不思議がまた1つ。2012/12/25
Ami
0
考古学ってロマンです。早速遺跡巡りをしたくなりました!2017/05/27