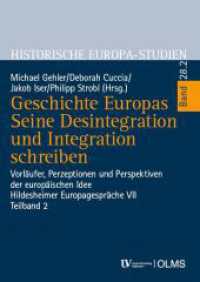内容説明
長野県の東端、北相木村の山間を流れる川の岩陰で、いまから一万年以上前、縄文早期はじめに縄文人が生活していた跡がみつかった。彼らが使用した土器・石器、精巧な縫針・釣針、海で採れた貝の装飾品、保存状態の良い人骨などから当時の暮らしぶりを再現する。
目次
第1章 太古の人類を求めて(岩陰に太古の人類をさがす;どのようにして岩陰はできたか)
第2章 分厚い生活の痕跡を掘る(生活の跡はどの深さに;遺跡はどこまで広がる;多方面の分析で追究)
第3章 縄文早期はじめの生活を追う(いつやって来たのか;豊富な食料;精巧な道具;火を焚く;移動する生活;縄文のアクセサリー;岩陰生活の悲劇)
第4章 変化する生活をさぐる(変わる出土遺物;岩陰に埋葬された縄文人;岩陰に腰を落ち着ける;早期縄文人が歩いた地)
第5章 その後、栃原岩陰は(縄文集落の出現と岩陰;山住みの民を求めて)
著者等紹介
藤森英二[フジモリエイジ]
1972年、埼玉県生まれ。明治大学第二文学部卒業。北相木村考古博物館学芸員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐藤一臣
4
骨角器を作る際の砥石や穀擦石などが遺物として出ている。土器には補修穴があり、壊れた土器に穴を穿ってそこに紐を通して再利用していたようだ。黒曜石の産地を転々としながら、黒曜石で作った石器を活用して生活するという移動生活をしていたらしい。まだ完全なる定住生活とまではいっていないようだ。抱き石や屈葬はすでにこの早期に出現している。石器は二次加工も施し、原材料もチャートを活用するようになっている。人骨の復元をすると顔は思ったよりもほっそりとしているそうだが、これは縄文早期に特異らしい。なぜだろうか?2023/05/17