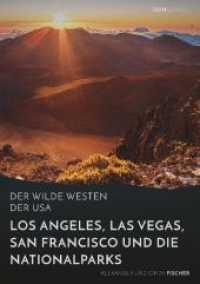内容説明
長野県の中央部、松本平に奈良時代から現在まで一二〇〇年間、途絶えることなく人びとが暮らした村が発見された。東山道沿いの要衝の地にあり、牧経営で栄えた村は時代ごとにその姿を変えながら戦国時代の争乱をも乗り越えて、したたかに生き抜いてきたのである。
目次
第1章 一二〇〇年つづいた村
第2章 律令制とともに成立した村
第3章 変動する村
第4章 古代から中世へ
第5章 消える村とつづく村
第6章 新たな発見へ
著者等紹介
原明芳[ハラアキヨシ]
1956年、長野県生まれ。信州大学教育学部卒業。長野県埋蔵文化財センター、長野県教育委員会文化財・生涯学習課、松本市内の小学校の勤務を経て現在、長野県立歴史館考古資料課長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
もるーのれ
4
松本平での発掘調査業務に当たるに際して拝読。考古学だけでなく歴史地理学などの視点もあって面白い。緑釉陶器などが多数出土するのも新興領主層の存在を窺えて興味深いし、その居住形態が平安時代くらいまでまだ竪穴であるのも畿内とかからすると驚きである。2024/07/14
ずしょのかみ
0
長野県立歴史館にいらっしゃる、原先生のお書きになった本。原先生は考古学以外の領域もお詳しい。憧れます。2015/05/21
杣人
0
仕事で松本の古代集落を掘るから再読。松本平における集落形態の変遷を明らかにする。歴史地理学で議論されている中世集村化現象と絡めて発展させられないだろうか。2024/03/27