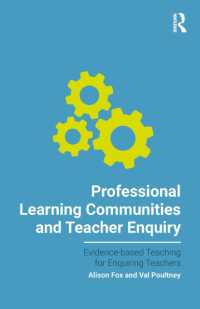内容説明
六世紀、赤城山南麓に三代にわたって大型前方後円墳がつくられた。墳丘には埴輪が立ち並び、白石を敷き詰め赤く塗られた石室には多くの副葬品がおさめられた。小像のついた筒形器台は、朝鮮半島とのつながりを物語る。この大型古憤から東国豪族の勢力を追究する。
目次
第1章 開かれた奥津城
第2章 最初につくられた前二子古墳
第3章 豪族の栄華を語る中二子古墳
第4章 巧みな石室づくりの後二子古墳
第5章 埴輪が林立する小二子古墳
第6章 上野地域の豪族
著者等紹介
前原豊[マエハラユタカ]
1953年群馬県生まれ。国学院大学文学部史学科考古学専攻卒業。群馬県藤岡市教育委員会を経て1982年から群馬県前橋市教育委員会で埋蔵文化財保護行政、大室古墳群の発掘調査、保存整備などに携わる。現在、埋蔵文化財保護課課長補佐(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月をみるもの
12
榛名山の 525年の噴火で保渡田古墳群や金井東裏遺跡周辺の集落が甚大な被害を受け、より東側に上毛野の活動の中心が移動した。そこに建設されたのが、この大室古墳群。6世紀後半、ここは間違いなく日本で最も栄えてた地域だったのだ。2018/11/12
rbyawa
3
e294、東国というのは大雑把に今の関東と東北、東日本の地のことのようなんですが、古代史においては重要視されていなかったものの、どうも日本全土で前方後円墳が消えつつある6世紀の頃に東国では盛況だったとか、この前に読んでいた同じシリーズの埼玉古墳群だとちょうど上毛野の豪族に圧迫されたらしいとかそんな話もあったなぁ。埴輪なども共通、ただし埼玉よりもこちらのほうが短かったり簡略化されたものが混ざっていたりもしますね。北からのみ南からのみ見ることを想定して作られたってのは初めて聞いたんですがどういう意味なんだろ?2014/10/21