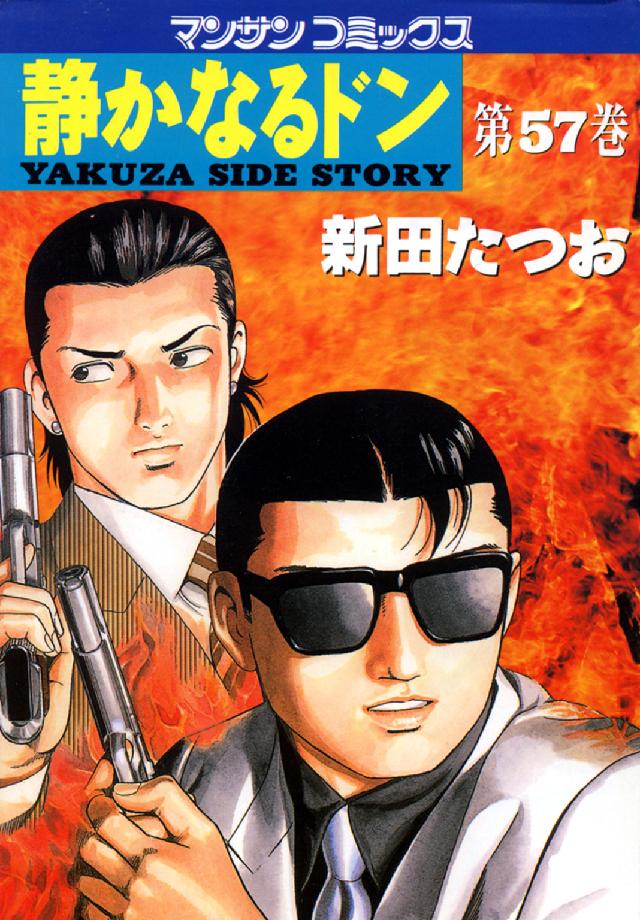内容説明
奈良県・三輪山の麓に広がる纒向(まきむく)遺跡。二世紀末に突然あらわれ、四世紀中頃に突然消滅したこの大きな集落は、邪馬台国の有力な候補地として浮かびあがってきた。祭祀場跡や大溝、東国や西国からやってきた人びとの痕跡、纒向型古墳などから追究する。
目次
第1章 三世紀の都市・纒向(三輪山の麓に広がる遺跡;邪馬台国の時代)
第2章 交通の要衝の地・纒向(特殊器台の発見;最初につくられた大溝;纒向へやって来た人びと;ヤマトから東国、西国へ向かう人びと;鍛冶―ツクシ型送風管の動き;物流センターとしての纒向)
第3章 纒向の祭祀(新しいカミ;カミと王の共食儀礼;祭殿と導水施設;ヤマトの神山と王権)
第4章 纒向から広がってゆく墳墓(纒向型古墳から箸中山(箸墓)型古墳へ
纒向型古墳
箸中山(箸墓)型古墳
新王権による旧王権への祭祀)
第5章 纒向は邪馬台国か(纒向が邪馬台国でなければなにか;邪馬台国東遷説と纒向;邪馬台国であることの証とはなにか)
著者等紹介
石野博信[イシノヒロノブ]
1933年、宮城県生まれ。関西大学大学院修了。兵庫県教育委員会、奈良県立橿原考古学研究所副所長兼附属博物館館長を経て、徳島文理大学文学部教授、香芝市二上山博物館館長、兵庫県立考古博物館館長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Shoji
56
私自身、纒向遺跡の現地へは何度か足を運んでいます。2009年に発見された三棟の大型建物物の遺構、箸墓古墳、周辺の古墳群、あるいは山の辺の道を訪れる度、この地がヤマト政権誕生の地であることは確信します。でも、邪馬台国が築かれ卑弥呼が君臨したことはやはりロマンの域を抜け出せません。もちろん、邪馬台国畿内説に賛成の立場です。この本は、纏向遺跡を史実をもとに解説しつつ、邪馬台国の決定打が出てくるのは後世の発掘に委ねる立場をとっています。纒向遺跡はたまたま発掘されたごく一部分に過ぎないと。確かに。2018/09/30
月をみるもの
16
2008年出版なので若干古びてはいるが、それでも纒向遺跡のレビューとしては圧倒的によくまとまっている。今度行く時には持参していかなくては。。。最後の章で、邪馬台国の存在地に関する決定的な証拠は、金印ではなく封泥の発掘であろうとあって、納得させられた。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%81%E6%B3%A52019/02/11
chang_ume
6
土器視点からの検討が詳しく、年代観としては寺沢編年との相違を都度指摘しながら、石塚と箸墓について前者をより古相(2世紀末)、後者を新相(3世紀末)に置いて、石塚と箸墓の被葬者を別系譜と想定する。ただ箸墓の被葬者像が本文中で台与と崇神で揺れるなど、読みにくい箇所も散見。また外来系土器の高割合から纒向遺跡を「都市」とみる立場ですが、正方位大型建物群や導水施設(下水処理では)の性格への大胆な論及もあって、本書だけではにわかに判断しがたいところも。箸墓の二重周濠復元図など、いくつかの図版が楽しい。2024/08/14
みにみに
3
巻向遺跡周辺の古墳の説明がわかりやすかった。2015/03/19
hyena_no_papa
2
感想は他の方が適切に書かれているので割愛。図版も多く、しかも綺麗。吉野ヶ里遺跡以降、「邪馬台国の候補地」といえる遺跡が九州には出現していないことをみても、もはや邪馬台国の所在地論争の大勢は決したと言っても過言ではないと思う。