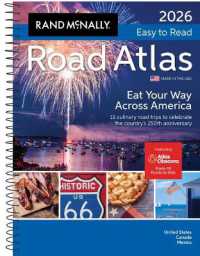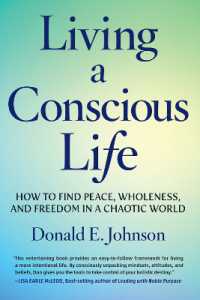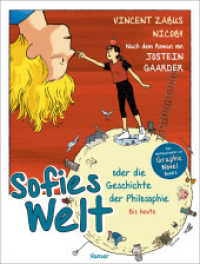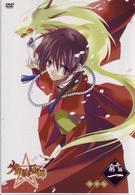内容説明
水産資源の減少と利用規制が議論されるなか、ナマコをめぐるエコ・ポリティクスを追う。グローバルな生産・流通・消費の現場を歩き、資源利用者が育んできた固有の文化をいかに守り、地球主体の資源管理を展望できるのかを考えた。
目次
ナマコをめぐるエコ・ポリティクス―環境主義下の世界に生きる
1 エコ・ポリティクスとコモンス(ダイナマイト漁の構図―環境問題への視角;ガラパゴスの「ナマコ戦争」―資源管理の当事者性)
2 ナマコを獲る(フィリピンのナマコ漁―マンシ島の事例から;日本のナマコ漁―北海道と沖縄の事例から)
3 ナマコを食べる(イリコ食文化―歴史と現在;中国ナマコ市場の発展史―大連の市場調査を中心に;ソウルのナマコ市場―チャヂャミョンとタマナマコ;イリコ・イン・アメリカ―グローバル化時代のナマコ市場)
4 ナマコで考える(同時代をみつめる眼―鶴見良行のアジア学とナマコ学;サマ研究とモノ研究)
生物多様性の危機と文化多様性の保全
著者等紹介
赤嶺淳[アカミネジュン]
1967年、大分県生まれ。1996年、Ph.D.(フィリピン学、フィリピン大学)。日本学術振興会特別研究員(PD)、国立民族学博物館COE研究員を経て、名古屋市立大学人文社会学部准教授。東南アジア地域研究、海域世界論、フィールドワーク技術論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イボンヌ
8
ナマコをめぐるフィールドワーク。ナマコをめぐる多様性と可能性。松茸と同じく希望の光になりそうです。 2021/01/10
ヒナコ
4
東南アジアの島嶼部世界の海洋ネットワークと、乾燥ナマコの流通を軸に展開される、ダイナミックな人類学。 鶴見良行の『ナマコの眼』の視点を受け継ぎ、著者は環太平洋地域一帯を、ナマコを求めてフィールドワークしている。そうした過程で見えてくるのは、現代資本主義の世界システムである。→2020/06/03
Hiroki Nishizumi
2
自分にとってナマコ本と言えば鶴見良行であるが、その思想、方法論ばかりか社会科学的ナマコ研究そのものの後継者が現れていたとは知らなかった、驚いた。導入部は地球環境としてのエコ・ポリティクスから入り、そしてナマコ漁の歴史と現状について実に丁寧に調べている。干しナマコは中華料理くらいしか利用しないが、その需要元である中華料理についてもヌーベル・シノワーゼの盛行などの報告も怠っていない。文章も幅があり読んでいて引き込まれる。他の著書、あるいはフィールドワーク記録についても読みたくなった。良かった!2014/09/01
メルセ・ひすい
2
13-124 赤61 華僑のカネと胃袋 乱獲と珍味の危機 ダイナマイト漁と華僑とカネ 水産資源の減少と利用規制が議論される中、ナマコのグローバルな生産・流通・消費の現場を歩き、資源利用者が育んできた固有の文化をいかに守り、地域主体の資源管理を展望できるのかを考える。 2010/07/22
北田覚
0
環境問題ってほんっとに複雑!! マクロな視点でミクロを見ないと見誤りますね。 読む価値ありますよ!2012/05/26