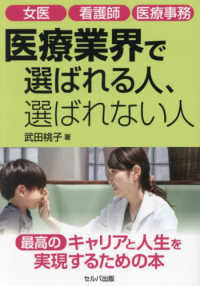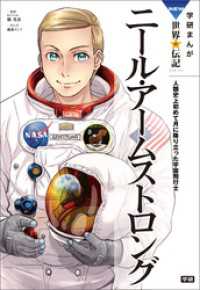内容説明
関東平野の東端、霞ヶ浦の南岸の台地に広がる陸平(おかだいら)貝塚には、いまでも途方もない量の貝塚の堆積が、周辺の自然豊かな景観とともに残されている。内湾の恵まれた海産資源を獲り、日本列島屈指の大貝塚をつくりあげた陸平縄文人たちの暮らしに迫る。
目次
第1章 霞ヶ浦の恵み(陸平貝塚を訪ねる;霞ヶ浦沿岸の貝塚)
第2章 貝塚を調べる(内海に浮かぶ島;貝層のあり方 ほか)
第3章 陸平縄文人の暮らし(集落の痕跡;漁撈の道具 ほか)
第4章 大型貝塚のなりたち(陸平遺跡群;対岸の貝塚群 ほか)
第5章 陸平への情熱(日本人による最初の発掘調査;地元に残された研究者の足跡 ほか)
著者等紹介
中村哲也[ナカムラテツヤ]
1963年、東京都生まれ。明治大学大学院文学研究科考古学専攻博士前期課程修了。現在、美浦村教育委員会、学芸員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月をみるもの
12
考古学の考古学って感じがたまらない。"茨城県稲敷郡美浦村に所在する陸平貝塚は、---- 多くの研究者によって調査され、同貝塚に関わる学術標本が東京大学に多数収蔵されている。これらのうち、明治期に由来する標本・資料は、日本先史考古学研究の創成過程の記録として、特に学史的な意義を有するものである" http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DJinruis/okadaira_2017/hajime.php2020/07/28
月をみるもの
12
モースの指導を受けた二人の東京帝大生、佐々木と飯島(のちにどちらも教授となる)は、日本人として初めて遺跡の発掘と報告書の作成を手がけることとなる。その遺跡が、縄文早期〜後期にいたる4000年の間継続的に人が暮らし続けた陸平貝塚。湖畔で積み重ねられた、長い長い人の営みの集積。2019/09/28