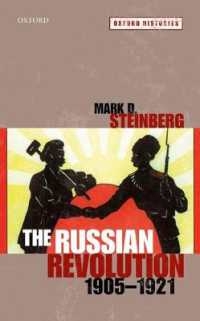内容説明
近代国家形成途上の明治期日本において新たにカテゴライズされた、大人でも子どもでもない「少女」という存在。妻となり母となる役割を担う前の彼女たちには、いかなるジェンダー規範が求められたのか。新進の研究者が膨大な資料から女性史研究の空白部を明らかにする画期的論考。
目次
近代国家における女性の国民化
第1部 「少女」の規範化(近代国家における「少女」期の位置づけ;「愛情」規範と「純潔」規範―相克する二つの教育目的;「美的」規範―精神美と身体美;少女雑誌における規範の展開;実践教育としての「園芸」―ケア役割の予行)
第2部 象徴としての「少女」像(浪漫主義文学と美術における「少女」像;白馬会における花と女性の表象;白百合に象徴される規範としての「少女」像;転落の狭間に置かれて―少女小説に描かれた二人の「少女」;転落の狭間に置かれて―少女小説に描かれた二人の「少女」)
著者等紹介
渡部周子[ワタナベシュウコ]
2001年千葉大学大学院文学研究科修士課程修了。2004年千葉大学大学院社会文化科学研究科博士課程修了。博士(文学)。現在、千葉大学大学院人文社会科学研究科特別研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
rbyawa
2
j104、こう言ったらなんだが私はわりと「家のための犠牲の女」という考え方に一部賛同しているところがあるのだが、「清く正しく」まではいい、「美しくして男を満足させるために生きよう」と言われてるとさすがに意味がわからず、男が罪を犯し、女がその責任を取ることこそが求められている、とたくさんの資料を使って示されていると「そこになんの合理性が…」と悩むことになった。多分なのだが自分の意思感情を持つべきではないと書くことが出来なかった代わりの美しくあれ、の概念かな…(それを書くと欧米人に叱られる)。捩れてんなぁ…。2019/09/11
ひろゆき
2
妊娠可能な体になってから妻になるまでの女性を少女と定義。明治期に少女の規範がどのように彼女らに与えられていったかを、文芸、美術運動などの分析からも説きおこす。良妻賢母という国家による動かせないゴールがあるため、性的純潔は守らせる必要があり、少女の肉食的な行動は抑圧される(純潔規範)。が、そのため、無事婚姻に至るためには、男から選んでもらう必要があり、男にとって好ましい美的対象物になることが少女には求められる(美的規範)。そのため少女たちの周りには教化を狙う、さまざまな装置が配置されたのでありましたとさ。2012/04/17
ちり
0
“女性の持つ精神的な美質が、身体的に可視的に発露するというロジックからなる「美的」規範は、異性愛男性の愛情の発言の条件を容貌の美へと収束した”2017/05/10
春猫
0
「(純潔を表象する)白百合」「愛の客体」が本書のキーワードだろう。図像に詳しい著者の力が発揮されている。故意かどうかはわからないが、近代以前に菫(すみれ)の持っていた性的な意味を近代の文学者が「貞操」の意味を持たせているところが面白かった。余談だがともかく注が充実している。2015/02/17
moni
0
明治期にどのようにして“少女”が形成されていったかを論じている本。現在の少女像にも通じるものがあるので、読んでいて面白い。ただ、やはり明治期の男性知識人の考え方は自分にとっては気持ちの悪いものだなと感じられた。もちろんこの点は性別と時代のギャップがあるので、どうしても仕方ないことだと思うけれども。2012/03/05
-
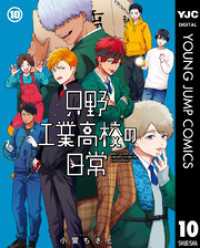
- 電子書籍
- 只野工業高校の日常 10 ヤングジャン…
-
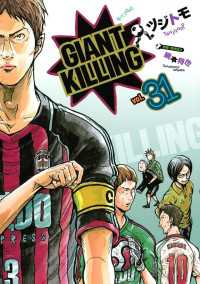
- 電子書籍
- GIANT KILLING(31)