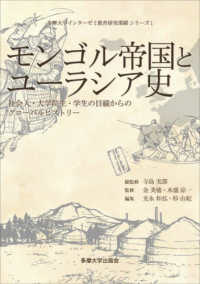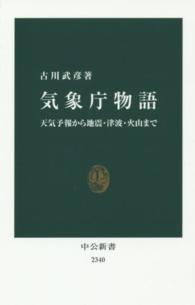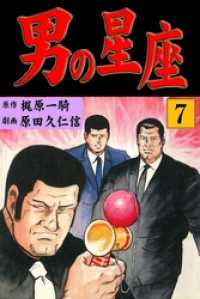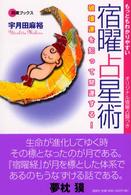内容説明
会津盆地の大型の前方後円墳・会津大塚山古墳は、三角縁神獣鏡が出土した日本列島最北端の古墳である。それは古墳時代のはじまりの頃すでに、東北に有力な首長が登場したことを物語る。周辺の古墳・弥生遺跡を含めて、北の古墳時代社会が成立していく過程に迫る。
目次
第1章 会津大塚山古墳の発掘(東北で最初の大型前方後円墳の学術調査;発掘調査開始 ほか)
第2章 測量図を作り直す(精度をあげた測量調査;新測量図からわかったこと)
第3章 ぞくぞくと見つかる古墳群(一箕古墳群の発見と調査;宇内青津古墳群の再評価 ほか)
第4章 北陸からきた土器(土器は語る;北陸北東部からの人びとの移住)
第5章 会津盆地の古墳時代(突然の変化;古墳の出現 ほか)
著者等紹介
辻秀人[ツジヒデト]
1950年10月30日生まれ。1980年東北大学大学院文学研究科博士課程後期単位取得満期退学。福島県立博物館の建設準備に携わり、開館後6年間博物館の運営にあたる。東北学院大学文学部、同大学院文学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月をみるもの
6
大学の住所である一箕という地名は、「箕にひとつづつ土を運んで山(〜古墳?)をつくった」という言い伝えから来ているらしい。そもそも会津という地名の由来が古事記(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E9%81%93%E5%B0%86%E8%BB%8D )にあるのだ。。 著者曰く、「この説話には、かつて大和王権の一員として活動した会津の勢力の記憶が反映されているのだろう」とのことで、土器や住居跡の解析から、この会津の勢力は北陸から移住してきた可能性が高いらしい。2018/07/07