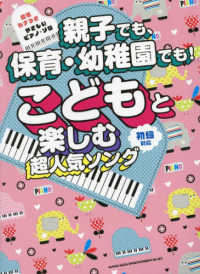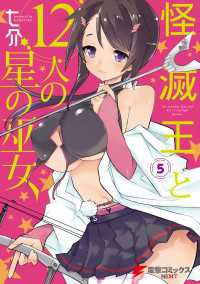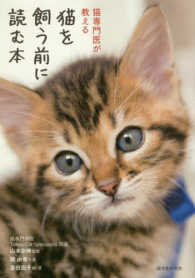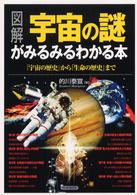内容説明
玄界灘に浮かぶ孤島・沖ノ島。照葉樹林におおわれた巨岩群に古代祭祀の世界が残されている。岩上・岩陰の“神殿”とそこにおかれた貴重な奉献品の数々は何を意味するのか。大陸・韓半島の遺跡・遺物との比較検討から、沖ノ島祭祀遺跡の意義を明らかにする。
目次
第1章 神体島、沖ノ島(玄界灘の孤島、沖ノ島;神域への序章 ほか)
第2章 沖ノ島の発掘(学術調査のスタート;巨岩上の調査 ほか)
第3章 豊かな遺物とその祭祀(岩上の神殿;岩陰の神殿 ほか)
第4章 沖ノ島をめぐる国際情勢(沖ノ島祭祀に注目した二人の学者;沖ノ島と百済 ほか)
著者等紹介
弓場紀知[ユバタダノリ]
1947年、奈良県生まれ。1973年、九州大学大学院文学研究科修士課程修了。京都橘大学文学部文化財学科教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
びっぐすとん
12
職場本。今月末、義父の四十九日で福岡へ行く際に、夫が「前乗りして寄ってきたら?」と言ってくれたので夫とは別行動で寄ることに。少しは勉強してから行こうと借りてきた。沖ノ島の全体像はまだまだわからないが、貴重な宝物が雨ざらしで岩陰に奉納されているというイメージとは少し違うようだ。 「質より量、見た目」という面もあった時代もある。縄文時代はアシカが棲息していて、祭祀の島ではなく漁場であったこと、大陸との交流がいつの時代にも伺えること、明治以降軍事施設があったことなど驚いた。 2024/10/13
月をみるもの
11
これ読んだらめちゃめちゃ行きたくなったんだけど、もはや上陸すること自体が不可能ってことなのかな。。。https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG15H4R_V10C17A7CC1000/2019/02/01
りー
9
祭祀跡の細かい図面や、巨石群の立体模型写真などが詳しく解説されています。沖の島の発掘や研究の流れをざっくり掴むには良い本。図版も豊富。それにしても、朝鮮半島とのつながりを感じる遺物が沢山。うーん。「日本」というくくりの中で古代史を考える限界を感じる。特に百済のことをもっと知りたくなってきました。2019/08/18
Windseeker
5
宗像大社の沖津宮がある沖ノ島遺跡に興味を持ったので購入。新泉社の「遺跡を学ぶ」シリーズは、きちっとした学者による、手軽で読みやすい入門書が欲しい時にはうってつけで、さっと読めるボリュームと豊富で鮮やかな写真に惹かれて、しばしば買い求めている。今回も期待を裏切られず、日本とアジアとの架け橋にあたるロケーションを取り扱っているだけに、知的好奇心を大いに刺激された。2012/05/03
坂津
1
宗像大社の沖津宮をまつる神体島であり、2017年には世界遺産に登録された沖ノ島。古墳時代から祭祀が行われており、多くの遺物が発見されていることは把握していたが、島内の遺跡の配置図や複数回に及ぶ具体的な発掘内容、銅鏡や金銅製馬具類などの出土状況についての解説が充実しているため、非常に参考になった。祭祀遺跡としての側面が注目されがちな沖ノ島だが、それ以前の縄文・弥生時代の土器や石器、魚介類や獣の骨も出土しており、筆者も指摘するように、神体島という固定観念で捉えてしまう現代人に相対的な視点を提供している。2022/04/17