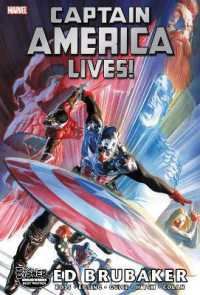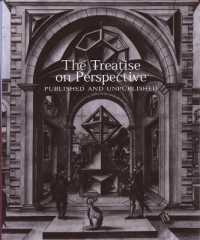内容説明
東京大学・本郷キャンパスは戦火をまぬがれ、その後急激な再開発がおこなわれなかったため、江戸時代の遺構が良好な状態でのこされていた。上は藩主から下は奉公人まで数千人は暮らしていたといわれる「江戸の小宇宙」加賀藩本郷邸の姿を考古学から明らかにする。
目次
第1章 発掘された江戸屋敷
第2章 御殿空間を探訪する(溶姫の御守殿;藩邸の中枢・表御殿;隠居御殿;庭園)
第3章 詰人空間を探訪する(東御門と東御長屋;足軽・聞番長屋;上級藩士が暮らした八筋長屋)
第4章 考古学からみた藩邸の暮らし(藩主の饗応;藩士たちの生活道具;ゴミが語る暮らし;便所が語る暮らし;遺物が語る暮らしのうるおい)
第5章 江戸のミクロコスモス
著者等紹介
追川吉生[オイカワヨシオ]
1971年5月5日東京生まれ。明治大学大学院博士前期課程修了。明治大学考古学博物館での嘱託勤務を経て、現在、東京大学大学院人文社会系研究科助手。日本考古学専攻
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
-

- 電子書籍
- キュロス~死すべき運命の王子【タテヨミ…