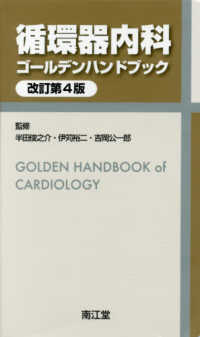内容説明
ピアノが誕生して楽器として進化する背景には産業革命があった。メーカー同士が競った技術革新と市場開拓が相互に影響しあって商品として普及していき、十九世紀の中産階級の台頭と軌を一にして富の蓄積と誇示の象徴として量産され、「繁栄する未来」を予感させた。日本への導入と伝播もすくい取りながら、ピアノと近代産業化する社会との関係を考察し、身近なピアノの誕生秘話に迫る。
目次
第1部 ピアノの誕生―楽器の向こうに「近代」が見える(戦争と革命が発展を促す;産業の楽器;ヴィルトゥオーソの時代;ピアノという夢;ピアノ狂騒曲;自動楽器;日本のピアノ)
第2部 近代産業とピアノ―ベートーヴェンとリストの苦悩(ピアノと鉄の文化;ベートーヴェンとピアノ;フランツ・リストと十九世紀社会;十九世紀社会の音楽―労働と消費、家庭と国家の力学のなかの音楽;兼常清佐と西洋音楽)
著者等紹介
西原稔[ニシハラミノル]
1952年、山形県生まれ。桐朋学園大学音楽学部教授、音楽学部学部長。18、19世紀を対象にした音楽社会史、音楽思想史を専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
柳 真佐域
10
ピアノの構造が知りたくて選んだ本だったが、どちらかというと作曲家とピアノの関係についての話が主でピアノ図鑑の方が得るものは大きかった。ピアノの普及は歴史的に見て、裕福な家庭がその象徴としてピアノを購入することからということがわかり、その家庭の女性達は皆ピアノを習わされたということだったが、その割には女性の作曲家を知らないので不思議に思った。時代から女性よりも男性が強かったのだろうが、才能のある女性作曲家も必ずいたはず。大量に新譜が生産され、廃棄された時期もあって、その中に名曲もあったのではなかろうか。2018/05/29
春
0
凄く良い本でした。ピアノの発展を、時代の流れ、そこで変化する人々の趣向から追って書かれた文献はなかなかないので。ピアノについて、新しい視点から歴史を知ることが出来、とても勉強になりました。2014/07/14