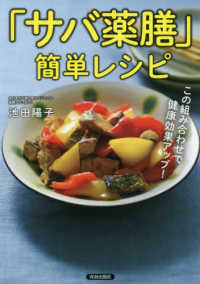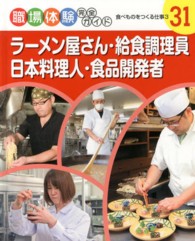出版社内容情報
権威性を漂白されたように見える「クラシック音楽」は、実際は多様な側面から「音楽」全体を規定しつづけている。クラシック音楽が内包するポリティクスを、グローバリゼーション、ポピュラー音楽との関係性、歴史、聴衆などの視角からあぶり出す論考集。
第1章 「クラシック音楽」の新しい問題圏――「音楽の都ウィーン」の表象と観光人類学 渡辺 裕
1 音楽学と「文化研究」
2 「クラシック音楽」と「観光」
3 「音楽の都ウィーン」という表象
4 「音楽散歩」とは何か?――「音楽遺跡」の発見と変容
5 メディア・イベントしての「ニューイヤー・コンサート」
第2章 「クラシック」によるポピュラー音楽の構造支配 増田 聡
1 クラシック・ロック? 「現代音楽」?
2 音楽言説としての「クラシック」
3 クラシカリゼーション
4 「クラシック」言説の実体化――「大地讃頌」事件
5 著作権制度と「クラシック」言説
6 逆向きの視線――「ポップ言説」からみたクラシック音楽
第3章 レクイエムとしてのクラシック音楽 清水 穣
1 聖なるものとしてのレクイエム
2 脳内麻薬としてのクラシック音楽
3 電子音楽の源流
4 二十世紀のレクイエム
第4章 戦時下のオーケストラ――日響・東響・大東亜響の活動にみる 戸ノ下達也
1 国策と音楽の関わり
2 アジア太平洋戦争期のオーケストラ活動
第5章 クラシック音楽愛好家と
内容説明
「帝国の音楽」としてその出自をもち、「高級」という記号として流通・機能しているクラシック音楽の現在形を、グローバリゼーションと観光、ポピュラー音楽との関係性、語られ方、歴史、聴衆、生態学などの視角から照射する。
目次
第1章 「クラシック音楽」の新しい問題圏―「音楽の都ウィーン」の表象と観光人類学
第2章 「クラシック」によるポピュラー音楽の構造支配
第3章 レクイエムとしてのクラシック音楽
第4章 戦時下のオーケストラ―日響・東響・大東亜響の活動にみる
第5章 クラシック音楽愛好家とは誰か
第6章 クラシック音楽の語られ方―ハイソ・癒し・J回帰
第7章 距離と反復―クラシック音楽の生態学
著者等紹介
渡辺裕[ワタナベヒロシ]
1953年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科教授。専攻は音楽学
増田聡[マスダサトシ]
1971年生まれ。国立音楽大学・明治学院大学・法政大学ほかの非常勤講師、日本ポピュラー音楽学会理事。専攻は音楽学、文化社会学、メディア論
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- スペイン学 〈第21号〉