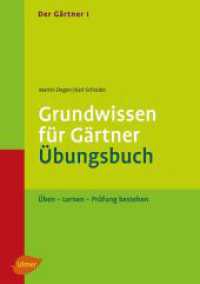出版社内容情報
女でもなく男でもない、聖にして俗、神に仕え、石つぶてを浴び、春をひさぐ者──ヒジュラ。カメラを片手に彼らの生きざまを追いつづけて17年。多数の瞠目の写真と平明な文章のなかに、混沌の大地インドに住まう第三の性が実像を結ぶ。
1 カルカッタ――世紀末的混沌に息づく不浄の神々
2 デリー――ヒジュラ社会の“光”と“闇”
3 アジメール――タール砂漠に現出したヒジュラの原風景
4 北インドと南インドの寺院――その精神風土と究極の相違
5 ボンベイ――売春地帯、あるいは未来への乾いた眼差し
あとがき
内容説明
女でもなく男でもない、聖にして俗、神につかえ、石つぶてを浴び、春をひさぐ者―ヒジュラ。混沌の大地インドに住まう第三の性が、瞠目の写真と平明な文章が形づくる空間のなかの実像を呼ぶ。
目次
1 カルカッタ―世紀末的混沌に息づく不浄の神々
2 デリー ヒジュラ社会の“光”と“闇”
3 アジメール―タール砂漠に現出したヒジュラの原風景
4 北インドと南インドの寺院―その精神風土と究極の相違
5 ボンベイ―売春地帯、あるいは未来への乾いた眼差し
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
トムトム
30
本来は、生まれつき男でも女でもない半陰陽の方を神聖視する風習。現在ではただのヌーハーフ!とはいえ美輪明宏さんが謎の存在であるように、今でも神聖視されている面もあるそうです。その本人の誇りというか、表現というか。強さであり弱さであり。どんな人でも、普通とされる人でも。生きていくのは大変だと思いました。2022/06/23
gelatin
5
★★★★ いやぁ、知らなかった。最近読んだ小説にヒジュラについて触れられている部分があって、興味を引かれてこの本にたどり着きまして。写真があるのがすごく大事で、すごくいい。文化論や民俗学でなく、今生きている人たちの話。もちろん学術的な価値もあろう。性も多様であるという認識などいかほどのものかと思わされる。受容や共存といった現代語では語れない在り様。ヒジュラたちの混沌と美、哀切としたたかさ、少しの剽軽さ。あまりに圧倒されて、彼らもカレー食べてるんだよな…などとくだらないことを考えてしまったよ。2024/08/29
まゆ
4
卒論で性的マイノリティ、主に性同一性障害について扱ったので、ヒジュラについては興味があった。この本は取材はよくされている。しかし著者は写真家であり、専門家ではないため、著者の感想ばかりが目につき少し物足りなさを感じた。しかし、20年前のインドでのヒジュラの実態を大まかに知ることはできた。2015/01/25
まよ
3
インドの男でも女でもないヒジュラといわれる人々について。LGBTなどの概念がなかった時代に、自分のセクシャルを「ヒジュラだ」と定義することができること、ヒジュラとしてのコミュニティがあり男でも女でもなく生きていけること。それにより生きやすくなったりした人がいたのだろうか。昔、日本では精神障害者が神がかり的な存在として集落などで受け入れられていた話を連想して、そういうふうにコミュニティから見て異端の人を受け入れる仕組みを作り上げる人間社会て面白いなと思った。言葉選ぶのが難しいですが。2023/03/12
かいけん
2
こういうセクシャリティが当たり前に許容される社会は素晴らしい。アウトカーストというポジションがインドではどのような扱いなのかが不勉強なのだけど、ただ実際問題としてつける職業も限定的だしかなり社会的には厳しいんだろうな。そういう風に産まれたからそういう風に生きるのだ、という考え方はインド的というか。時代や地域によって与えられるポジションや風習などが変容している様も興味深い。取材からまた20年近く経過してるけど、今はどんな社会になっているんだろうか。2014/01/18