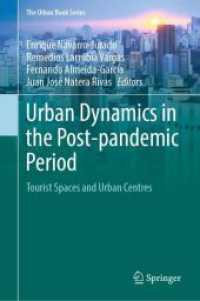出版社内容情報
近年、児童虐待が社会問題化している一方で、社会的養護のもとで暮らす子どもへの支援も注目を集めている。これまで援助の「あるべき姿」などを中心に議論されてきたが、現場ではどのような困難が経験され、施設のありようをめぐって何が問題とされているのか。
本書では、児童養護施設や母子生活支援施設、里親などを対象に、各施設のフィールドワークを積み重ね、関連する政策文書や史料を丹念に読み込む。それらをとおして、児童養護施設で求められる「家庭」のあり方、施設で過ごす子どもや職員が抱える葛藤、愛着概念の変容、発達障害と施設の関係性、母親という規範などを浮き彫りにする。
医療、教育、ジェンダーなどの多角的な視点から、子どもを養護する現場や制度が抱える規範や規律を照射して、「家族・家庭」と「施設の専門性」の間に生じるジレンマを明らかにする。
内容説明
児童養護施設や母子生活支援施設、里親などの子どもを養護する現場や制度が抱える様々な規範を、医療・教育・ジェンダーなどの多角的な視点から浮き彫りにして、「家族・家庭」と「施設の専門性」の間に生じるジレンマや子どもが直面する困難を明らかにする。
目次
序章 「社会的養護の社会学」のインプリケーション
第1部 社会的養護と「家庭」(母性的養育の剥奪論/愛着理論の再構築と里親委託―一九七〇‐二〇〇〇年代の里親関連専門誌の分析から;社会的養護政策での「家庭的」の意味とその論理―二〇〇〇年代以降の政策関連資料から;児童養護施設が「家庭的」であること―中規模施設と地域小規模施設の比較から)
第2部 子どもの教育体制と施設内規律(児童養護施設で暮らす子どもたちの“仲間”と“友人”―施設と学校でともに生きるということ;児童養護施設の職員は子どもの医療化とどう向き合ったのか;母子生活支援施設の母親規範を問う―介入手段としての生活の決まりに着目して)
終章 二〇〇〇年代以降の社会的養護と社会規範・専門概念・ネットワーク
著者等紹介
土屋敦[ツチヤアツシ]
1977年、神奈川県生まれ。関西大学社会学部教授。専攻は福祉社会学、家族社会学、子ども社会学
藤間公太[トウマコウタ]
1986年、福岡県生まれ。京都大学大学院教育学研究科准教授。専攻は家族社会学、福祉社会学、教育社会学
野崎祐人[ノザキユウト]
1996年、愛知県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程。専攻は家族社会学、歴史社会学
三品拓人[ミシナタクト]
1989年、岐阜県生まれ。日本学術振興会特別研究員。専攻は家族社会学
宇田智佳[ウダトモカ]
1995年、石川県生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程。専攻は教育社会学、家族社会学、子ども社会学
吉田耕平[ヨシダコウヘイ]
1983ねん、徳島県生まれ。東北文教大学人間科学部准教授。専攻は社会福祉学、医療社会学
平安名萌恵[ヘンナモエ]
1994年、沖縄県生まれ。立命館大学大学院一貫制博士課程、日本学術振興会特別研究員。専攻は家族社会学、オキ罠学、ジェンダー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
てくてく
ぷほは
-

- 電子書籍
- 一次元の挿し木 宝島社文庫