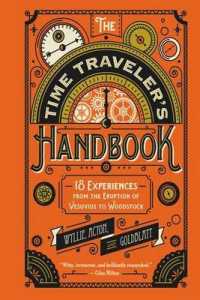出版社内容情報
戦後、日本女性と外国人兵士、特にアメリカ兵との間に生まれた「混血児」は、現在は「ハーフ」としてあるイメージをもって語られるが、いまも昔も、様々な差別と日常的に接してきた。
性暴力と売春、貧困と格差、優生思想と差別など、重層的な社会的困難を背負ってきた彼/彼女たちは、「混血児」としてどのような教育を受け、労働に従事して、戦後日本の社会を生きてきたのか。
占領・復興期から高度経済成長期、そして現在までの聖ステパノ学園における混血児教育の実践を縦糸に、各時代の混血児の社会的な立場や語られ方を横糸にして、「混血児」をめぐる排除と包摂の戦後史を活写する。
序 章 戦後史の裂け目――?血の政治学?と?出会いの教育学?のはざまで
1 なぜ「混血児」の戦後史をいま問うのか
2 混血児をめぐる従来の研究と本書の分析視点・内容との差異
第1章 占領・復興期の混血児誕生――優生保護法の下で生存する[敗戦から一九五〇年代前半まで]
1 敗戦後セクシュアリティ統制の遺産――優生思想にさらされる混血児
2 澤田美喜の実践にみる混血児の別学という人格主義――幼稚園の教育実践
3 幼稚園から小学校へ――ステパノ学園の実践と苦悩
第2章 日本「独立」後の公立小学校の混血児教育――日本人として学ぶ[一九五〇年代中葉]
1 文部省の混血児教育の方針――いじめへの全学的な対応
2 公立小学校での共学という平等主義――実母と教師に支えられて
3 公立小学校の苦悩と教師たちの試み――制度内での改革と日本人への同化
4 同化を超えた連帯を目指して――優生という排除の論理に抗いながら
第3章 高度経済成長期前半の混血児教育――経済主義の下で生きるために学ぶ[一九五〇年代後半から六〇年代前半まで]
1 保守化する教育行政――管理主義下の道徳と能力
2 自治と協働の仲間づくりの徹底化――ステパノ学園の実践
3 技能教育へ――生きて働くために
第4章 高度経済成長期後半・低成長期の混血児と日本人の子との出会い――経済主義の下で教育と労働をつなぐ[一九六〇年代後半から七〇年代後半まで]
1 大衆雑誌にみる混血児イメージの定着と日本社会への包摂――才能と汚辱
2 進学と就職のはざまで揺れる混血児――ブラジル農業移民という最後の選択肢
3 高度経済成長の喧騒を超えて――日本社会へのいくつかの包摂パターン
4 周縁化された子どもたちの出会いの場として――ステパノ学園の実践
第5章 低成長時代の周縁化された子どもたちの連帯――多様性を再生し開く挑戦[一九八〇年代前半から現在までを見据えて]
1 澤田美喜の死(一九八〇年)と新たな挑戦――社会へ広く開かれる学園
2 支え合い互いにケアし合う場として――多様性のなかでの心の回復
終 章 戦後史を超えて――?包摂と排除?か?つながりと連帯?か
1 戦後史のなかの?現在性?――?現在的課題?としての混血児教育の方法
2 教育学と歴史学を架橋する混血児の戦後史
3 〈選別社会〉に抗う〈歴史のなかの教育〉
あとがき
上田 誠二[カミタ セイジ]
著・文・その他
目次
序章 戦後史の裂け目―“血の政治学”と“出会いの教育学”のはざまで
第1章 占領・復興期の混血児誕生―優生保護法の下で生存する(敗戦から一九五〇年代前半まで)
第2章 日本「独立」後の公立小学校の混血児教育―日本人として学ぶ(一九五〇年代中葉)
第3章 高度経済成長期前半の混血児教育―経済主義の下で生きるために学ぶ(一九五〇年代後半から六〇年代前半まで)
第4章 高度経済成長期後半・低成長期の混血児と日本人の子との出会い―経済主義の下で教育と労働をつなぐ(一九六〇年代後半から七〇年代後半まで)
第5章 低成長時代の周縁化された子どもたちの連帯―多様性を再生し開く挑戦(一九八〇年代前半から現在までを見据えて)
終章 戦後史を超えて―“包摂と排除”か“つながりと連帯”か
著者等紹介
上田誠二[カミタセイジ]
1971年、栃木県生まれ。横浜国立大学ほか非常勤講師、首都大学東京オープンユニバーシティ講師。専攻は現代史、教育史、音楽史。著書に『音楽はいかに現代社会をデザインしたか―教育と音楽の大衆社会史』(新曜社、主に同書の研究史上の意義が評価されて日本教育史学会の第28回石川謙賞を受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hitotak



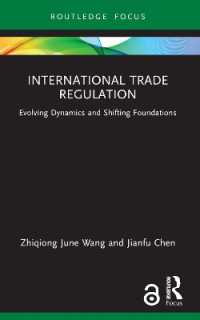
![裏千家茶道点前と棚の扱い 〈4〉 入子点(風炉・炉) 透木の扱い(炉) 棚[三友棚] 淡交テキスト](../images/goods/ar2/web/imgdata2/44730/4473046044.jpg)