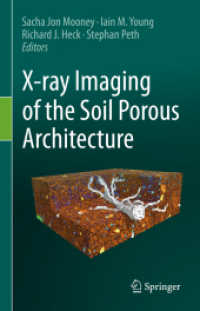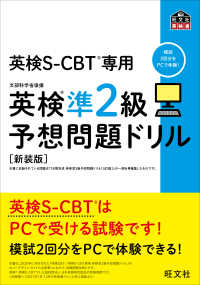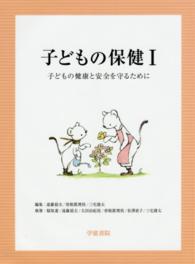- ホーム
- > 和書
- > 社会
- > 社会問題
- > マスコミ・メディア問題
内容説明
私たちが模型を作る場合、モノと向き合っているが、それを通して向こうの「実物」に思いを馳せてもいる。このとき、模型という「モノ」は、ある種の「メディア」になっている。「モノがメディアになる」という問題意識のもと、日本社会のなかの模型について、歴史・現在・理論の三つの側面から解き明かす。
目次
模型というモノ/メディア
第1部 歴史(日本の近代化と科学模型;帝国日本の戦争と兵器模型;戦後社会とスケールモデル/プラスチックモデル)
第2部 現在(情報消費社会とキャラクターモデル/ガレージキット;グローバル化・デジタル化と拡散する模型)
第3部 理論(ポピュラー文化における「モノ」―記号・物質・記憶;「モノ」のメディア論―メッセージ・ネットワーク・オブジェクト)
模型のメディア論
著者等紹介
松井広志[マツイヒロシ]
1983年、大阪府生まれ。大阪市立大学大学院文学研究科後期博士課程単位取得退学、博士(文学)。愛知淑徳大学講師。専攻はメディア論、文化社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Mentyu
2
日本における模型の文化史を通して、ヒトとモノの関係を分析するという筆者の試みは、読んでいてとても面白い。ただ、やはりこの手の研究ではモノ(あるいは物質性)が人間にとって重要だと主張するあまり、その先の分析が弱くなる傾向にある。ヒトにとってモノが重要だと明らかにした上で、それをいかにして社会分析に生かすのか追究すべき段階に来たのではないかと思う。2018/05/31
コウみん
1
模型の歴史からビジネスまで日本の模型はどんな影響を与えたのかについて書いた本。 まさか「ガンダムセンチネル」がガンプラブームに連関されたことに凄く驚いたが、日本のプラモデルはガンプラブームから始まったかも知れない。2022/02/04
とく
1
模型製作者は模型を作る場合、モノと向き合っているが、それを通して向こうの「実物」に思いを馳せてもいる。このとき、『模型という「モノ」は、ある種の「メディア」になっている』といういう考えの下、社会のあり様が時代と共に変わっていく中で、『模型』は製作者と何を媒介する役割を果たし、これからの社会の中で、どんな役割を果たしていくのか。自身も模型を趣味とする著者が社会学的に論考する。評者も模型が趣味であり、読み進めていく中で自分の好きなものと、深く向き合うことが出来、楽しい読書体験をする事が出来た。2017/08/26
johnlenon64
0
TRPGと模型(プラモデル)との類似性は以前から気になっていたのだが、なかなか論考するに機会がない。もしチャンスがあれば書いてみようと思うので、そのときのために備忘として記録する。 詳しくは下記のアドレスで col20241155模型のメディア論 時空間を媒介する「モノ」 https://kokutoarchives.cocolog-nifty.com/blog/2024/12/post-94d40b.html2024/12/01
佐々木大悟
0
思わず表紙買いしてしまったのだが、模型人として「模型というモノ」への見方が変わった一冊となった。博士論文レベルの諸論文をまとめた一冊とあって、内容は結構ハード。それでも「歴史」「現代」の部分は明治期からごく最近に至るまでの本邦の模型シーンの変遷を俯瞰できて、興味本位だけでも読み進めることができ面白かった。最後の「理論」については、ワタシ自身が社会学や哲学の素養を積み重ねてないのもあって理解が追い付かなかったが、それでも模型人として色々と考えさせてもらう価値ある時間を得ることができたと思う。2019/02/06