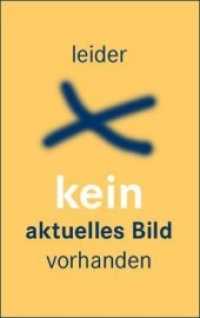内容説明
パフォーマンス化しキャッチフレーズ化する政治を筆頭に劇場と称される事象が頻発し、マスメディアとインターネットが作り上げるそれら熱狂的な騒動は爆発的な勢いで全国を席巻しては消滅していく。情報を受容し消費するはずの側があたかも「お祭り」の主役であるかのように幻惑され、劇場に躍り出ては大騒ぎを演じ続ける。テレビとWeb2.0が作り出すメディア空間、刹那的なものではあれ共同体を希求する「自己」、「物語の終焉」後に獲得された「物語」もどき、表出するためのコミュニケーションスタイルなどの切り口から、激情に身を任せる劇場型社会の「お祭り」を形式レベルと表層構造で解説し、メカニズムの深層にメスを入れる。
目次
第1章 東国原劇場の出現
第2章 「お祭り党」とフラッシュ・モブ
第3章 「お祭り党」の表層構造
第4章 テレビ的メディア空間の出現―Web2.0は「お祭り」を扱えない
第5章 物語の終焉―「お祭り」のマクロ構造1
第6章 物語と「お祭り」―「お祭り」のマクロ構造2
第7章 「お祭り」とコミュニケーション―「お祭り」のミクロ構造
著者等紹介
新井克弥[アライカツヤ]
1960年、静岡県生まれ。関東学院大学文学部教授。専攻はメディア論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おらひらお
2
2009年初版。小泉純一郎やそのまんま東等の事例を上げ、メディア主導もしくは魔術師主導のお祭りを分析したもの。図書館借用本なので、線が引けないのが残念ですが、学ぶところが多い本でした。2011/11/23
U-Tchallenge
1
劇場型社会というのは、平成中期頃から現在に至るまで見られる現象のように思う。そんなことを考えていて出会った一冊である。懐かしい小泉劇場や東国原英夫フィーバーが取り上げられており、劇場型社会というのがよくわかる内容となっていた。劇場型社会における「お祭り党」がなぜ発生することについての考察も興味深かった。このお祭りをどう飼い慣らすのかということは現代ではかなり重要な視点ではないだろうか、と思った。2024/02/13
D.N
0
バウマンと何が違うのかよくわからなかった2009/10/11
灘子
0
面白い視点だった。この人とお話ししてみたくなった。インスタグラムとかでも同じこと言えるよねー。 2021/01/31