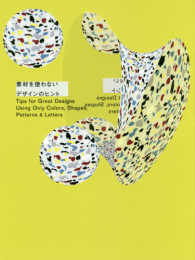内容説明
「仲間をつくれ」「働け」。的はずれを含めた多くの批判にさらされ、「回復」へと駆り立てられるひきこもりの“当事者”たち。対人関係の獲得や就労の達成という「社会参加」とそうすることの意味のはざまで、「なぜ働くのか/なぜ生きるのか」と彼/彼女らが抱いている不安や焦燥を、聞き取り調査をとおして描き出す。そして、「自己防衛戦略」や「存在論的不安」などの視点から、“当事者”たちにとって「ひきこもる」とはどのような経験なのかを浮き彫りにする。必要なのは“当事者”に共感することではなく、むやみに「回復」をめざさせるのでもなく、彼/彼女たちを理解することだと主張・提言する社会学の成果。
目次
第1章 問題意識―フィールドでの経験から
第2章 「ひきこもり」の社会的文脈
第3章 自己防衛戦略としての「ひきこもり」
第4章 自己を語るための語彙の喪失としての「ひきこもり」
第5章 人生における危機/転機としての「ひきこもり」
第6章 問うという営みとしての「ひきこもり」
第7章 生きていくことを覚悟する
第8章 「ひきこもり」再考
著者等紹介
石川良子[イシカワリョウコ]
1977年、神奈川県生まれ。横浜市立大学非常勤講師。専攻は社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
27
ひきこもりとは何のか。ひきこもり当事者への丁寧な聞き取りから考察がなされており、大変興味深く読みました。長期のひきこもりの実態として、働くことにどのように向き合うのかという問題があります。働くことが社会参加でるという社会規範があり、金銭的にも問題となるからです。しかし著者はそこに疑問を投げかけます。ひきこもり当事者が生きることを覚悟すること自体が当事者にとって大切なことであるからです。〈社会参加〉を強制する社会はひきこもり当事者を排除する社会であり、社会の在り方を問う必要性を著者は問うています。2015/09/16
とらじろう
23
ひきこもりの私にとってほとんど自分のことを書かれているような本で、就労で頭がいっぱいでも現実は全然進んでない というところでこの本を読み、とても参考になりました。一般就労も障害者就労も自分には厳しいのかなぁと最近思ったりもします。親死んだあとどうするかとか具体的に考えないと行けない年齢になってきたて、就労がゴールでないならば、まだましな方に進む、そういう星のもと生まれてきたんであろうか。就労してることによって社会にも出ているのではなく、ひきこもりも含めて社会という価値観が自分にとって便宜上の価値観。2018/12/09
あかたけ
5
”ひきこもり”という言葉ができたことによって、自分を語る語彙を得た人がいると知った。ニートとひきこもりは混同せず、それぞれに合った対応をしていくべきだとおもう。2013/11/23
saiikitogohu
3
「思うように生きられない自分を呪い、過去を反芻し、あのときこうしていればよかったと後悔を深め、周囲を恨み、なぜこんな自分になってしまったのかと嘆くーー。こうしたところから何とか抜け出そうと長年もがき続け、試行錯誤を繰り返すうちに、ここで『実存的疑問』と呼んだような問題に対峙せざるをえなくなった、あるいは対峙せずにはいられなくなった」(232)「Gさんは学生時代から働くことに対して恐怖感をもっていたが、そこで抱いていたイメージは非常に限定的なもの…「働くことに自分の時間をとられるのがとても怖かった」」2018/08/24
まつゆう
3
ひきこもりを扱った本は色々あるが、これが一つの達成点のような気がする。これを超えるような本は当分出ないのではないだろうか。2016/10/26