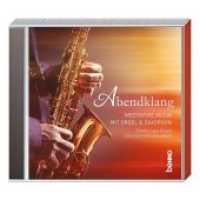- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
出版社内容情報
近代に入って発見され、さまざまに意味づけられてきた「子ども」は、本当に保護されるべき受動的な存在なのか? 駄菓子屋や黎明期の子どもの読み物などから、社会に積極的に参加していた子どもの姿をさぐり、21世紀の子ども観を展望する。
第1章 「児童の世紀」の光
1 二十世紀の夜明け
2 近代の矛盾とエレン・ケイの祈り
3 「児童の世紀」の光
第2章 「児童の世紀」と読書の喜び
1 精神の自由の獲得――近代公教育の普及と識字率
2 読む楽しみを知る――子どもと教科書
3 出版の近代化と近代読者の誕生
4 十九世紀末の子どもの読書体験
5 子どもの読み物の誕生――『こがね丸』の出版
6 子どもの読み物の黎明
第3章 子どもの消費生活と駄菓子屋
1 小波の生活と金銭
2 子どもの小遣い
3 ハレの日の縁日、ケの日の駄菓子屋
4 樋口一葉の駄菓子屋
5 駄菓子屋の誕生
第4章 「児童の世紀」の影
1 統制・禁止の対象になった子どもの読み物と駄菓子屋
2 〈子どもの領分〉に閉じ込められて
第5章 ふたたび光を求めて――個性としての〈子ども〉
1 大人と子どものバリア・フリー
2 権利の主体としての子ども
3 〈子ども〉という個性
あとがき
内容説明
近代的な子ども観の発見は子どもの権利を意識する一方で、子どもを“子どもの領分”に押し込めながら隔離し、いまや“子ども不在”の社会が形成されるまでになった。しかし、子どもは本当に与えられるだけの存在なのだろうか。社会が急速な変貌を遂げた20世紀初頭の駄菓子屋と読み物にかかわる子どもの姿をさまざまな文献を渉猟することで探り出し、子どもがみずから積極的に参加し選択する存在であったことをあきらかにする。そして、子どもは保護され育成される存在であるという固定観念から離れ、近代的な子ども観が与えた光と影を丹念に読み解くことで来るべき21世紀の大人と子どもの新たな関係性を探り、そのための子ども観を提示する。
目次
第1章 「児童の世紀」の光
第2章 「児童の世紀」と読書の喜び
第3章 子どもの消費生活と駄菓子屋
第4章 「児童の世紀」の影
第5章 ふたたび光を求めて―個性としての“子ども”
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
肉ちゃん