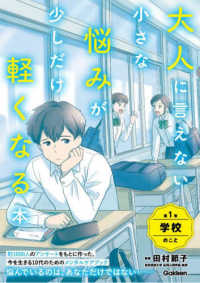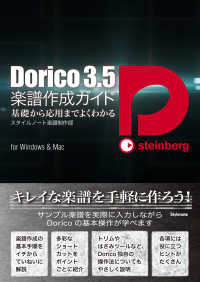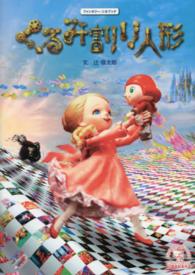内容説明
日本の近代国家形成期に和歌・短歌といった文化的な営みはそのナショナティの確立にどのような影響を及ぼしたのか。天皇巡幸、御歌所、歌道奨励会、教育学・心理学知との接合、題詠と歌会、愛国百人一首といったキーワードを手がかりに和歌・短歌の近代と政治性を明らかにする。
目次
序章 課題と方法
第1章 天皇巡幸を「よむ」こと―『埋木廼花』編纂の意味
第2章 「嗟歎の声音」の政治―高崎正風の歌論とその諸活動の検討
第3章 明治天皇「御製」のポリティクス
第4章 「旧派」の行方―大日本歌道奨励会の形成から衰退まで
第5章 「よむ」ことと心理学―「児童研究」誌における詩歌への期待
第6章 「和歌革新」前後―題詠と賀歌の変容
第7章 歌会における「自己」表現の試行―「アララギ」派歌人たちの題詠
第8章 「芸術」と国家への理路―佐佐木信綱とその和歌観の変遷
第9章 つくられる“愛国”とその受容―「愛国百人一首」(一九四二年)をめぐって
第10章 誰が「ヒロシマ」を詠みうるか?
著者等紹介
松澤俊二[マツザワシュンジ]
1980年、群馬県生まれ。名古屋大学大学院博士後期課程単位取得満期退学、博士(文学)。現在は桃山学院大学社会学部准教授。専攻は日本近・現代文化、文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。