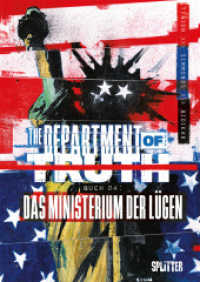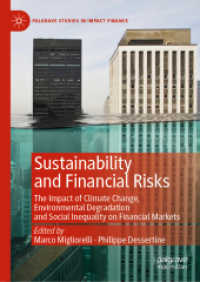- ホーム
- > 和書
- > 文庫
- > 学術・教養
- > 学術・教養文庫その他
出版社内容情報
【近代浪漫派文庫26 岡本かの子/上村松園】
収録作品
■岡本かの子
・かろきねたみ
・老妓抄
・雛妓
・東海道五十三次
・仏教(人生)読本ヨリ
■上村松園
・青眉抄ヨリ
【新学社近代浪漫派文庫】
刊行のことば
文芸の変質と近年の文芸書出版の不振は、出版界のみならず、多くの人たちの夙に認めるところであろう。そうした状況にも拘らず、先に『保田與重朗文庫』(全三十二冊)を送り出した小社は、日本の文芸に敬意と愛情を懐き、その系譜を信じる確かな読書人の存在を確認することができた。
その結果に励まされて、専ら時代に追従し、徒らに新奇を追うごとき文芸ジャーナリズムから一歩距離をおいた新しい文芸書シリーズの刊行を小社は思い立った。即ち、狭義の文学史や文壇に捉われることなく、浪漫的心性に富んだ近代の文学者・芸術家を選んで四十二冊とし、小説、詩歌、エッセイなど、それぞれの作家精神を窺うにたる作品を文庫本という小宇宙に収めるものである。
以って近代日本が生んだ文芸精神の一系譜を伝え得る、類例のない出版活動と信じる。
新学社
近代浪漫派文庫 全四十二冊
1.維新草莽詩文集
2.富岡鉄斎/大田垣蓮月
3.西郷隆盛/乃木希典
4.内村鑑三/岡倉天心
5.徳富蘇峰/黒岩涙香
6.幸田露伴
7.正岡子規/高浜虚子
8.北村透谷/高山樗牛
9.宮崎滔天
10.樋口一葉/一宮操子
11.島崎藤村
12.土井晩翠/上田敏
13.与謝野鉄幹/与謝野晶子
14.登張竹風/生田長江
15.蒲原有明/薄田泣菫
16.柳田国男
17.伊藤左千夫/佐佐木信綱
18.山田孝雄/新村出
19.島木赤彦/斎藤茂吉
20.北原白秋/吉井勇
21.萩原朔太郎
22.前田普羅/原石鼎
23.大手拓次/佐藤惣之助
24.折口信夫
25.宮沢賢治/早川孝太郎
26.岡本かの子/上村松園
27.佐藤春夫
28.河井寛次郎/棟方志功
29.大木惇夫/蔵原伸二郎
30.中河与一/横光利一
31.尾﨑士郎/中谷孝雄
32.川端康成
33.「日本浪曼派」集
34.立原道造/津村信夫
35.蓮田善明/伊東静雄
36.大東亜戦争詩文集
37.岡潔/胡蘭成
38.小林秀雄
39.前川佐美雄/清水比庵
40.太宰治/檀一雄
41.今東光/五味康祐
42.三島由紀夫
目次
岡本かの子(かろきねたみ;東海道五十三次;老妓抄;雛妓;仏教読本(抄))
上村松園(青眉抄(抄))
著者等紹介
岡本かの子[オカモトカノコ]
明治22年、東京に生れる。兄の大貫晶川、その友人谷崎潤一郎の感化で文学への眼を開かれ、初めは与謝野晶子に師事して短歌に早熟の才を示した。大正元年に処女歌集「かろきねたみ」を刊行の前後から宗教への関心を深めていくなかで続けられた作歌は、昭和4年の「わが最終歌終」に至る。昭和11年「鶴は病みき」で小説家としての新たな出立を遂げ、その後「母子叙情」「老妓抄」をはじめとする力作を次々に世に問うて、短時日に文壇に確乎たる地歩を築いた活動は、昭和の文学史上に偉観をなした。昭和14年に歿するが、豊饒で、大河の滔々と流れるような情感の漂う作風は、遺作の「生々流転」「女体開顕」等に一貫する
上村松園[ウエムラショウエン]
明治8年、京都府に生れる。幼少時から絵を好み、十二歳で京都府画学校に入学するとともに四条派の鈴木松年に師事し、その後幸野楳嶺、次いで竹内栖鳳に学んだ。早くから現れた天賦の画才は、明治33年の「花ざかり」に華かに開花し、京風俗を写すなかで美人画のジャンルを拓く。大正7年の「焔」、昭和11年の「序の舞」、同13年の「砧」等、女性の美に対する理想や憧憬を描き出して端正な彩管は、晩年において円熟の度を加え、「夕暮」あるいは「晩秋」に見る画格の高雅さは、近代日本画の女流作家として他に並ぶものがない。昭和18年に「青眉抄」(六合書院刊)。同23年、女性として初めて文化勲章を受章し、翌24年歿
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。