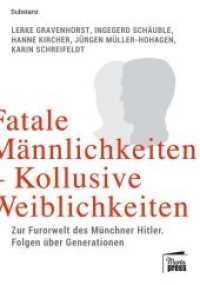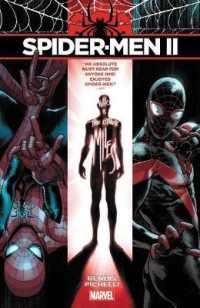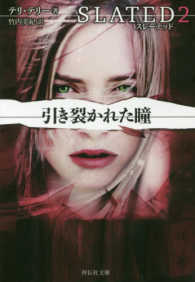- ホーム
- > 和書
- > 文庫
- > 学術・教養
- > 学術・教養文庫その他
目次
島木赤彦(自選歌集 十年;柿蔭集;赤彦童謡集より;歌道小見;随見録(抄))
斎藤茂吉(初版 赤光;白き山;思出す事ども;ニイチエの墓を弔ふ記(滞欧随筆より)
島木赤彦臨終記
斎藤茂吉之墓)
著者等紹介
島木赤彦[シマギアカヒコ]
明治9年、長野県に生れる。長野師範学校に学び、同県内で教育者の生活を送りながら、はじめ新体詩を作る時期を経て「アララギ」に加わり、大正2年、中村憲吉と合著で処女歌集「馬鈴薯の花」を出版した翌3年に上京、斎藤茂吉らに代わって「アララギ」の編集に当たる。その後「切火」「氷魚」「大虚集」の各歌集において進境を示す。同15年に歿した
斎藤茂吉[サイトウモキチ]
明治15年、山形県に生れる。第一高等学校時代に作歌を始め、師事した伊藤左千夫を中心に同41年「アララギ」が創刊されると、東京帝大で精神医学を修める傍ら、左千夫を助けて同誌の編集に従う。大正2年刊行の第一歌集「赤光」は、一躍作者の名を世に高くした。青山脳病院長の業に携るなかで、「アララギ」を率いて旺盛に続けられた制作は、戦争で郷里に疎開後の戦後の作品を収める「白き山」に至るが、文化勲章を受章した翌々昭和28年に歿(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ダイキ
2
「赤彦ほどの人物は、ゲーテ以降の世界文学史上に何人もないのである。しかし芭蕉が野ざらしから軽みへ入つた神の道については、赤彦の晩年に於てまだ現れなかつた。悲しいことである。まことにそれこそ近代日本の最大の悲劇の一つである。」〈明治の俳句/保田與重郎〉、「神が遠くから来られるといふことや、遠くの神を招くといふすべを、忘れた詩人は不幸である。彼(赤彦)はつひに最後的にいびつで、くらく、陰気である。詩は生れるもの、豊富な生産のものであるのに、かゝる人の詩は、堅く窮つてゐる。」〈文学的時務観/保田與重郎〉2016/10/18