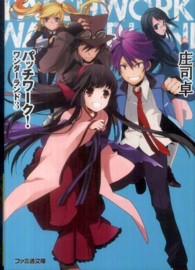内容説明
本書は、歿後の昭和五十八年六月末、京都の自邸書庫から未発表の原稿が見出され、翌年十月に新潮社から『日本史新論』と題されて公刊されたものである。六〇年安保に揺れる世情に触発され、昭和三十五年から翌年にかけて発意、執筆された文章でありながら、当時の政治状況に依った時務論ではなく、この国の成り立ちと生成を説き明かすことによって国の行末に警鐘を鳴らさんとした、抵抗の文芸にほかならない。
目次
述史新論
皇大神宮の祭祀
教育について
わが絶句
鬱結ノ記
「日本人の美的生活」といふことについて
歴史の信実
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
双海(ふたみ)
14
本書は、歿後の昭和五十八年六月末、京都の自邸書庫から未発表の原稿が見出され、翌年十月に新潮社から『日本史新論』と題されて公刊されたものである。六〇年安保に揺れる世情に触発され、昭和三十五年から翌年にかけて発意、執筆された文章でありながら、当時の政治状況に依った時務論ではなく、この国の成り立ちと生成を説き明かすことによって国の行末に警鐘を鳴らさんとした、抵抗の文芸にほかならない。(カバーより)2014/06/14
人民の指導者
1
ここで語られるのは、新嘗祭=天皇制を中心とした一種の国家有機体説である。ただし、戦前は神儒一致に抗し、戦中は国家総動員の近代主義に耐え、戦後は進歩主義から沈潜することでこの理想を保田は貫き通したこと、そして保田が貫き通したその場所が、まさに農村や古民家で営まれる保田の実生活だったことは決して無視すべきではない。本書に対する最も有効な批判は、網野善彦による稲作中心史観への反駁であろう。2011/06/24