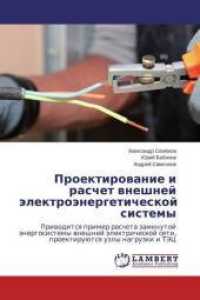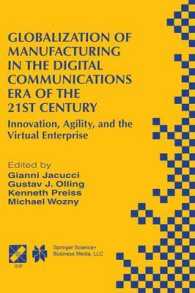内容説明
紙から電子の時代へ。激動する出版業界を、販売面から支えるリアル書店。流通する「知」の最前線にある挫折、芽吹く希望。紙の本と生身の人間とが交差する、12の人生を追う。
目次
第1章 中小書店の戦い方
第2章 ベストセラーの「舞台裏」
第3章 「本屋大賞」の未来
第4章 異能の人、終わらない夢
第5章 「書店人」のキャリア
著者等紹介
山本明文[ヤマモトアキフミ]
北海道留萌市生まれ。名古屋大学工学部卒業後、日本生活協同組合連合会に勤務、品質検査部門に携わる。その後、自ら志願してコープ出版へ出向。月刊誌のデスクに任じられた後、フリーライターとして独立。小売業・流通業、地域興しなどの分野で、意欲的に執筆を続ける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しなもん
25
書店のお仕事や意義、パターン配本、返品率の問題など、詳しく深く知ることができました。 インタビューされた書店員の方の経歴やどのように働いてこられたかについてもとても参考になりました。わたし自身、心を揺さぶられた本との偶然の出会いが書店であって、書店員を目指そうと思ったので、とても興味深かったです。本屋大賞やPOP、新刊書店で古本を置くなどの書店員さんの人と本の出会いをつなぐ工夫に感動しました。人にしかできないこと。 わたしもそんな書店員さんになりたい…* ざっと読みなのでまたじっくり読み直したい。2016/02/25
蓮
7
本の向こう側にいる人達が垣間見た気がしました。2011年出版の本ですが、相変わらず問題は山積みで、書店をとりまく状況はより一層悪くなっているのかもしれません。でもこの本に出でくる人や、出てこないけれど同じくらい頑張っている多くの人がいることを嬉しく思います。2015/05/21
らっそ
6
こういう本を読むと、やっぱり本は本屋さんで買おうと思う 気になる一文:データがあるから“データに意味がない”ということも分かる/三島由紀夫を知っているかどうかより、カバーをちゃんと掛けられる方が偉い/売れてる理由は売れているから/実際に『千里の道』を前にしたら、中々前向きに考えられるものではない/未来が定まっていない以上、すべての絶望は勘違いである/デジタルばかりでは頭の中の構造が平板になってしまいます2012/07/24
きいち
6
現場で当事者として立ち向かっている、そのみなさんの戦いっぷりを読むだけで元気になれる本。「本屋大賞」や「POP」といった売るための仕掛け、自由に仕入をするための仕組み、どれも主体的に仕事をするための努力で、ああ、自分も自分の現場でがんばりたい、と思わせる。『「本屋」は死なない』とよく似てるのにまた違った読後感なのは、どれも都市圏の話で集客よりも販売の話題が中心だからかなあ。2012/04/02
緋莢
6
出版不況が続き、本がなかなか売れない現在。出版点数が増え、日々、送られてくる大量の本。そんな中で、一冊でも多くの本を売ろう、埋もれてしまった本を再び陽の当たる場所に出そうと奮闘する書店人たちがいた。ベストセラーの入荷しにくい中小の書店で頑張る人たちから、POPや仕掛け販売で売り場からベストセラーを作った人たち、そして、一度は去った書店という職場に戻ってきた人まで、書店で働く12人の姿を書いた作品。2011/12/11
-

- 和書
- 椰子の浜辺の「螢の光」