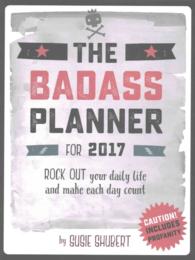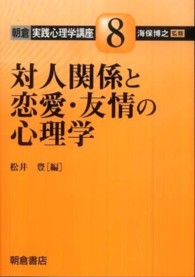目次
血液・免疫(血液の組成;造血;物質輸送;赤血球;止血機構;血小板と血漿 ほか)
内分泌(内分泌系の概観;視床下部と下垂体;甲状腺・副甲状腺(上皮小体)
副腎 ほか)
著者等紹介
山本一彦[ヤマモトカズヒコ]
東京大学医学部教授(アレルギー・リウマチ内科)。1952年生まれ。大学卒業後、雰囲気の良かった当時の物療内科に入局、次第に免疫学に惹かれ、ドイツ癌研究センターに留学、遺伝子解析を中心とした免疫学の研究を続けた。帰国後、内科で自己免疫の研究をしようと一念発起し、自己抗原遺伝子の研究や自己抗原に対する免疫応答の研究を始め、現在はT細胞レセプターを中心とした抗原特異的免疫制御法の開発を推進中
松村讓兒[マツムラジョウジ]
杏林大学医学部教授(解剖学)。1953年生まれ。北海道大学卒業後、解剖学第三講座に伊藤隆教授最後の大学院生として入り、造血細胞特に巨核球の定量形態学的研究を行う。1984年、解剖学第二講座(児玉譲次教授)に入局、肉眼解剖学研究の手法を学ぶ。1989~91年には連合王国レスター大学のEngland博士のもとに留学、発生学特に原始生殖細胞について研究を行う。最近は児玉教授より譲られた胎児頭蓋コレクションを用い、頭蓋の形成の研究を進めている
多久和陽[タクワヨウ]
金沢大学医学系研究科教授(生理学)。1954年生まれ。2年間の研修の後東京大学第4内科に入局、尾形悦郎教授の薫陶を受け内分泌学を専攻するに至った。1985年、米国エール大学医学部ハワード・ラスムッセン教授(Ca2+イオンがセカンドメッセンジャーとして機能することを最初に主張した研究者)のもとに留学、平滑筋収縮・弛緩時のイノシトールリン脂質加水分解反応、細胞内Ca2+動態、蛋白質リン酸化を明らかにした。帰国後内科を経て、1991年より基礎医学教室で研究教育に従事
萩原清文[ハギワラキヨフミ]
JR東京総合病院主任医長(リウマチ・膠原病科)。1971年、東京都生まれ。1995年、東京大学医学部卒業。2001年、東京大学大学院医学系研究科修了。医学博士。専門はアレルギー、膠原病内科(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 第11話 SNSがキラキラ見えて苦しい…