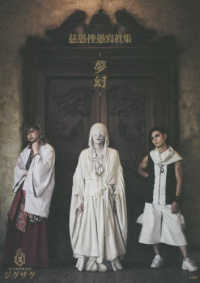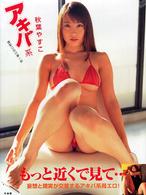内容説明
西欧起源のマルクス主義にとって、より東方の社会をどう理解するのか、つねに難しい問題であり続けたが、社会主義の祖国が作り上げたマルクス主義教義は、マルクスが本来抱いていた独特の「アジア的社会」に対する認識を否定してしまった。マルクス主義とその歴史学におけるアポリアとしてあった、「アジア的なるもの」をめぐる論争史。
目次
第1章 日本におけるアジア的生産様式論争―戦前編
第2章 日本におけるアジア的生産様式論争―戦後編一九四五‐一九六四年
第3章 日本におけるアジア的生産様式論争―第二次論争編一九六五‐一九八二年
第4章 二十世紀中国におけるアジア的生産様式論の変遷
第5章 中国におけるアジア的生産様式論争―一九七九‐一九八九年
第6章 中国におけるアジア的生産様式論の後退と東方社会理論の興起
第7章 西欧におけるアジア的生産様式論争の勃発
著者等紹介
福本勝清[フクモトカツキヨ]
1948年北海道滝川市に生まれる。1978年明治大学第二文学部史学地理学科東洋史専攻卒業。1981年~84年北京大学歴史系留学。現在、明治大学商学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
トックン
0
戦後の分水嶺としてスガは「ハンガリー事件」と「スターリン批判」(1956)を挙げるが、それに『東洋的専制主義』(1957)出版を付け加えたい。著者ウィットフォーゲルはスターリンが黙殺していた「アジア的生産様式」を取り上げ、「水の理論」(水力社会論)へと練り上げる。スターリンの5段階の発展論には包括されないアジア的可能性=躓きの石として灌漑・治水による国家形成に伴う土地私有性の欠如がアジアにはあったがスターリン体制では、この論は憂き目を見た。日本では講座派的視点しか許さぬ状況が戦後暫く続いていたに等しい。2017/07/30