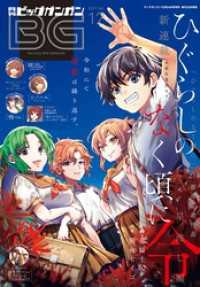内容説明
フォイエルバッハの「食の哲学構想」の解読を基礎に、現代日本の食の世界が抱えている諸問題を考察する。
目次
第1部 フォイエルバッハの「食の哲学」(「食の哲学」への道程;「身体」と「食」の構想;「食の哲学」入門―フォイエルバッハを参考に「食と宗教」について考える;ルードヴィヒ・フォイエルバッハ『犠牲の秘密、彼が食べるところのものである』(解読)
補稿:フォイエルバッハ研究の軌跡)
第2部 食と社会―現代日本の食の問題(コロナが変える「食(事)の世界」―「いのちと経済」で揺れる「食の思想」を考える
「孤食」について哲学する
“食”とイデオロギー
現代日本の“食”の問題とジェンダー
「食」のゆくえ)
著者等紹介
河上睦子[カワカミムツコ]
相模女子大学名誉教授。博士(文学)。総合人間学会理事。専門、哲学・社会思想(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
42
書名はフォイエルバッハのDer Mensch ist, was er ißt による(004頁)。1862年にこの言説をもつ著作を書いたが、注視されることはなかったという(021頁)。食べることは生きることの本質だと著者は示唆する(022頁)。日本の主食米価高騰で、私もそうだと思う(5月からは麺類ばかりが実情)。生命の本質は生命の外化Lebensäußerung にある(055頁)。哲学は事象の本質や意味の思考追求する学(081頁)。私は食を、人を良くするものと思っている(漢字のパーツの意味から)。2025/07/25
コバ
1
フォイエルバッハの「食の哲学構想」の解読を基礎に現代日本の食の問題を考える。 コロナやテクノロジーが食のあり方を大きく変えようとする中で、孤食なども増えている。 食べるという行為が人間にとってどのような意味を持つのか改めて考えるべき時に来ている。2024/03/31