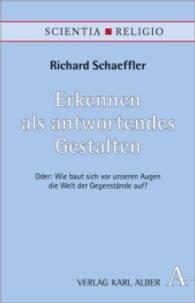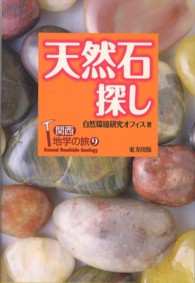感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
てれまこし
7
近代においては「呪術」「科学」「宗教」(そして「哲学」)は違うものだが、この区分はプロテスタントによる宗教革命後の発展であり(その淵源は古代ユダヤと古代ギリシアにまで遡れるが)、それ以前においてはそれらは厳密に区別し難かった。西洋の人類学者は科学の普遍性を信じ、「呪術」を未開社会における科学の代替物(「誤った科学」)と解した。しかし、呪術は必ずしも自然を支配・操作するための因果論的介入に還元されえず、「融即(participation)」の原理のもとで宇宙全体と一体化するパフォーマティヴな行為でもある。2025/05/29
いまにえる
2
呪術的精神が近代科学を生み出したという指摘や、逆に現代科学にも通じるような反例をうやむやにして処理する呪術にありがちなことなど、呪術、科学、宗教という区分の見直し、そして普遍的合理性を疑い、かつ相対主義も疑うような面白い本だった。2019/07/24
mittsko
2
大変すばらしい研究だと思った 著者タンバイアの優秀さは知っていたけど あぁやっぱりスゲェな…と痛感した 科学史/科学論の成果を軸において、「宗教・呪術・科学」を切り口にして展開される西洋精神史の概論、といったおもむき 先行研究の批判的なまとめだけで これだけのものが書けるんだから…学問にはまだやるべきことがありますね そして議論は 人類学者らしいアプローチで「普遍と特殊」の問題、さらには「知と言語と現象、さらには存在」へと接近していく ボクには細かな点での正誤を判断できないけど つよくオススメの一冊です2013/06/07
なぎこ
1
意外にも面白く、一気に読んでしまった。個人的に、<因果>と<融即>という2つの指向性の共存を論じている部分が参考になった。 2010/06/01
環世界
0
呪術や宗教、科学などとラベリングされるようなものを含む人間のあらゆる活動には「因果」と「融即」の双方が分かちがたく結びついていて、差異はその重点の置き方に過ぎないというのが骨子。かなりラトゥールの純化と翻訳の話に近い。面白かったのは、特定の尺度のもとでは「発展」はあると主張しているところ。スリランカ出身のタンバイアにしてみれば、すべては相対的であるとして煙に巻くような議論は、支配的な西洋人のマッチポンプというか戯れでしかないんだなと2020/01/01