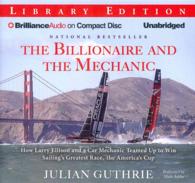感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
72
ほりんさんのレビューを拝見して手に取る。無償の愛とはこういうものなのだろう。作者は、優しいお母さん、もしくはひたすら甘やかしてくれたおばあさんを思って書いたのだろうか。読んでから題名を見て、まさにgiving tree だと切なくなった。ここから教訓を引き出すべきでないのだろう。子供とは愛だけもらって、でも忘れずに時々帰れば、疲れたら甘えれば、愛を与える方は満足するのかもしれない。2014/06/22
パフちゃん@かのん変更
61
村上春樹訳と本田錦一郎訳では私は本田錦一郎訳の方が詩的で好きですが、原文はどうなっているのか気になって読んでみました。まず、木はsheと表されており、母親あるいは年上の女性と言った感じでしょうか。少年はboyで、これは老人になってもboyです。本田訳でもおじいさんになっても「ぼうや」としていますね。落書き村上氏は「ぼくと彼女」でしたが本田訳では「たろうとはなこ」でした。原文では「M.E.&Y.L.」これはmeではなくイニシャルでしょうね。but not really.のところは少年が行ってしまったから。2014/05/17
Hideto-S@仮想書店 月舟書房
54
多分中学生の頃読んだ本。邦題の【おおきな】からの連想で、【木】は自然の象徴だと思ってました。男の子があまり幸せそうにみえないのは「自然に感謝する気持ちが足りないから」と考えていました。いい年の大人になって、オリジナルの英語版を初めて読み認識が変わりました。原文では【木】はsheと描かれているんですね。【木】は母性のようなものの象徴かもしれないと気づいたのです。その認識で本田錦一郎さんの訳と村上春樹さんの訳を読み比べると、また違う感想を持ちました。いろんな解釈ができるのは、それだけ深い本だからだと思います。2014/08/13
ほりん
24
数年前に,村上春樹が新訳を出して話題になりました。初めて読んだときは旧訳で読んでいたので,友情もしくは父性愛ととらえていましたが,原文がsheなので,やはり母性の愛なのでしょう。とにかく描かれているのは,最後まで与え続ける無償の愛の姿です。中学生になった息子と原文を読みながら,なんとも切なくなりました。息子は「うーん」と言ったきり。どう思ったのかな?2014/06/08
よし蔵
19
大学の図書館で初めて読んだことを覚えている。その時は日本語で、今回は英語で。シンプルなのにというか、シンプルだからなのか、泣ける。木は母のように少年を愛していたけど、少年は木に対して冷めていて大人になると貰うものだけもらって後は寄り付きもしなくなる。木が無償の愛を持ち続けることに胸が痛む。本当に木は幸せだったのかな。母親は子供がどんなことをしても許してしまうところがあるのかな。少年はどんなことを考えているんだろう。いろいろと考えさせられる深い本だと思う。2015/09/07
-

- 和書
- 日本の多国籍企業