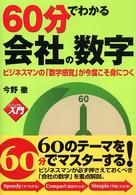内容説明
戦国大名・今川義元の「人質」だった家康は、いかにして天下取りを果たしたのか。そして織田信長との同盟時代や、豊臣秀吉の臣下に組み込まれていた苦難の時代を、どのようにして乗り越えていったのか。大河ドラマの時代考証を手掛ける著者が、最新の研究成果を取り入れつつ、新たな家康像を描き出す。
目次
第1部 駿府・浜松時代の前半生(強豪織田と今川の狭間で揺れる三河武士;信長と同盟、今川・武田氏を撃破;第3章 天下人秀吉と実力者家康の虚々実々)
第2部 大御所への道(関ヶ原の戦いの謎;ドキュメント・関ヶ原;関ヶ原の舞台裏;駿府大御所時代;名古屋城を築く;東西の手切れ、冬の陣・夏の陣)
第3部 徳川家臣団の検証(膨張し続けた徳川軍団;四天王の実像;家康ゆかりの静岡の名城)
著者等紹介
小和田哲男[オワダテツオ]
1944年、静岡市生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。現在、静岡大学名誉教授、文学博士、公益財団法人日本城郭協会理事長。専門は日本中世史、特に戦国時代史。NHK大河ドラマ『秀吉』『功名が辻』『天地人』『江~姫たちの戦国~』『軍師官兵衛』『おんな城主直虎』『麒麟がくる』『どうする家康』の時代考証を担当(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アーサー
8
再読◆この本ならではの主張は、家康が居城を浜松から駿府に移したことを「積極的に退いた」と解釈するという点(一般的な説は、秀吉との対決を避けるため)。五カ国、とくに甲斐を掌握するために甲斐に近い駿府に移転した。拡大した領土の最先端の近くに城を移すのは、信長の常套手段。それを家康は踏襲した◆他の家康本と比較していないので、上の主張がどの程度ユニークなのかはわからない◆家康は、逆境をプラスに捉える発想ができて、さらにバランス感覚に優れた人だなと思った。あと、情報収集にも長けている。2023/03/24
アーサー
7
通読◆2022年発行。本書は、発表済みの記事を再構成・加筆したもの。著者は大河ドラマ『どうする家康』の時代考証担当者◆新しい研究結果にも目を向け、真実の家康像を描き出す◆家康最大の功績は、戦国争乱に終止符を打ったことという。関ヶ原の戦いと大坂夏の陣が家康がらみの戦いだったことによる。「一国一城令」、「武家諸法度」により戦さのない時代に移行する法制化をすすめる。これらは秀忠の名で出されているが、実質的には家康の主導だった。そしてその後260年間の平和をもたらす◆三分の一は関ヶ原の戦い。図表は少なめ。2023/03/09
Abercrombie
2
大河ドラマ『どうする家康』の時代考証担当者が、今までに書いていた家康に関する文章をまとめたもの。わかりやすいが、繰り返しが多く、内容も簡略すぎ。歴史観もいささか古びている。2024/01/13
はる
1
以前に書かれたものを再構成などしています。けっこうわかりやすく読みやすい。2023/04/10
金田
0
人としてのなりと姿は時代や見方が変わっても、始末の良さに有るところに好感を持っている。関ヶ原の後から先まで起こりうることには十分に対策を立て放り出さなかった点では興味深いし、まあ相対する人には裏目が出た所もあるが、それだけでは説明のつかない人の生き方としても。そも幕末における動乱にまで話が尽きない歴史は面白い。2025/09/29