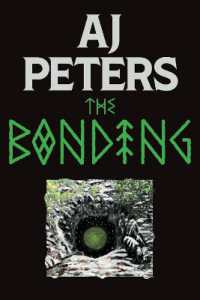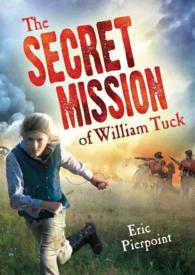内容説明
弥生人は偉大なる“人間の先輩”だ!登呂遺跡を舞台に、「土があれば生きていける」を実験する陶芸家のクレイジーな記録。
目次
第1章 土を焼くと、焼き物にな~る
第2章 アートロを始める
「登呂で、オレらは考えた。」展公開トーク『登呂キッチン』鼎談収録
「登呂で、わたしは考えた。」アフタートーク
著者等紹介
本原令子[モトハラレイコ]
昭和38年生まれ。陶芸家。多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン科卒業、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート(RCA)セラミックスアンドグラス修士課程修了。平成24年から静岡市にある弥生時代の遺跡「登呂遺跡」を舞台に社会実験を行うプロジェクト「ARTORO(アートロ)」をスタート。登呂会議代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
やすらぎ
178
地表面における日常がいくら加速し過ぎ去っても、大地を掘れば太古の時代が見えてくる。美術家本原令子さんのアートロのテーマは、土さえあれば生きていける。もっと自由に学びたい。それが始まりだった。陶芸家として登呂で考えたこと。岩や石、砂や粘土。縄文や弥生土器を実際に作ってみて、あぁここはこうしたかったのねと気持ちを知る。作る喜びに現実味を帯びてくる。野焼き。この方法で土器は自然に還れるという。土団子を作って数ヶ月放置すると分解の哲学の入口を理解できるという。昔に戻りたいのではなく今に繋がる何かを探し続けている。2022/12/23
榊原 香織
68
登呂遺跡に行くと弥生のカッコして稲作してる人たちがいるのだけれど、アートロ、てあれかナ? 土器を作り、米を作ることで、人間社会まで自然に考えるというプロジェクト。 市内安藤米店店主も登場 変わったお米屋さんだな、と思ってたら美大出身ナノネ 私の好きなキタアカリ(胚芽が大きい玄米)発見者も登場。 いろいろ興味深い2023/03/27
けんとまん1007
43
土。土があれば生きていける。土から食器が作れる。土があれば、食物が作れる。煮炊きをすることで、生物としての進化も促進される。そんな、社会実験でもあるアートロの活動の記録でもある。ここで大切なのが、自分たちで、実際にやってみるということ。そこからの学びもあれば、社会というものが発生し、諍いにもつながるということ。まるで、これまでの人類史をコンパクトにたどっているようでもある。興味深いだけでなく、ヒトの不可思議さも感じる。2021/01/28
yyrn
21
陶器に興味を覚えて美大に進みデザイン会社に勤めるも使い捨てられるパッケージデザインに失望し、英国にわたって陶芸を一から学び直した著者。登呂博物館の協議員になったことをきっかっけに縄文と弥生時代ではまったく異なる土器への関心から「土」をテーマにしたワークショップを立ち上げて、登呂の水田の土で土器を焼き上げたり、コメもみんなで作って自作の土器で炊くなどの作業を通じて様々なことに気づき、二千年前の人々の知恵を追体験していく、その過程がとても面白い。ぜひとも多くの人におススメしたい一冊だが、静岡新聞社の出版。2019/05/18
にきゅ
4
人間や自然について考えさせられました。去年の暮れに静岡県に移住いたしました。登呂遺跡には30年以上前に家族旅行で行きました。再訪したいですね。2020/06/03