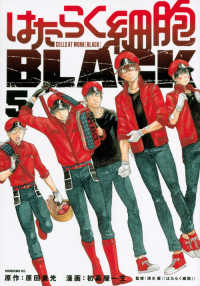内容説明
なぜ口語自由律なのか。現代詩の詩型としての主題を直視せよ―。なお底光りを放ち続ける黒田喜夫、石原吉郎らを表現論として現在に読み解き、詩が「凄味」をもった時代への環流を試みる。証言から提起へ、日本語の詩に根柢の問いをせり上げる、卓抜した批評集。
目次
詩が円熟するとき―はじめに
1 詩的60年代ノート(戦争体験をめぐって;谷川雁幻想;「列島」私考;黒田喜夫・六〇年代 ほか)
2 「犯罪」から「白鯨」(金時鐘『新潟』;佐々木幹郎『死者の鞭』;支路遺耕治『疾走の終り』;私的大阪文学学校事情 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なかたつ
0
「犯罪」および「白鯨」という詩誌の存在をこの著作で初めて知ることができた。著者はその両者の同人として深く関わり、その内部からこの両者の働きを振り返るのがこの著作の主旨であろう。だが、60年代に起きた安保闘争と詩との関わりや、金時鐘の働きなど、同時代の政治性と詩が相容れるものでもあった。黒田喜夫の飢餓論はサルトルを思わせ、石原吉郎・吉岡実などに対する考察もその背景を持って語られるものであった。語られなければ過去は存在しえないという大森荘蔵のテーゼのように、この著作で語られた60年代への一視線は貴重な資料だ。2014/01/16