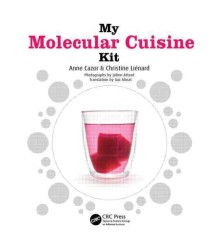内容説明
『言語にとって美とはなにか』から40年、伝統的な七五調に西欧近代精神を盛り込もうとした藤村、そこからの離脱を試みた初期象徴詩人。近代詩の様式の変遷を厳しく問い直す。
目次
詩学叙説―七・五調の喪失と日本近代詩の百年
詩学叙説・続―初期象徴詩の問題
新体詩まで
日本近代詩の源流
表現転移論1 詩人論序説4
表現転移論2 詩人論序説5
現代詩の問題
「四季」派の本質―三好達治を中心に
戦争中の現代詩―ある典型たち
近代精神の詩的展開
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ひろゆき
3
なんとなく寄り付かなかった、いまさらながらの初吉本隆明。かなりの日本詩人がバッタバッタとなで斬りにあってます。単なるブルジョア生活への憧れにすぎないとか通俗だとか。実も蓋もないですが、それがとても痛快。2014/02/25
1
再読。定型詩が崩壊した後に詩の根拠を喩法に求めるのだが、「意味」と「価値」を分けて前者は「散文」に、後者は「詩」にそれぞれ切り分ける。それは、透谷-藤村という「歌う」詩から、薄田-蒲原という「読んで考える」詩のパースペクティブの再編成を含意するものであろう。むしろ、川路柳虹-民衆詩派の口語自由詩は、薄田-蒲原の抑圧=隠蔽なのではないか。もちろん、平戸廉吉から始まる前衛詩運動から、春山行夫の詩の徹底的な「散文」化は、さながら抑圧されたものの回帰とでも呼ぶべきものであり、それは今でも未完結の問題である2017/09/01