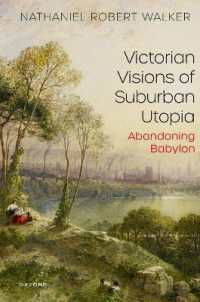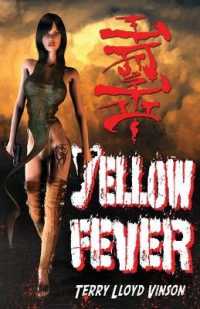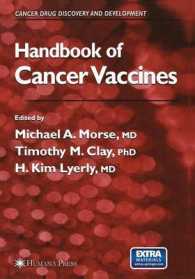内容説明
抒情の核たる「うた」の不在―近代のアポリアをいかに超えるか。日本近代詩に稀有な達成をみた萩原朔太郎・伊東静雄・中原中也の本質を、比類なき鋭利な解析力をもって「方法」のレベルまで剔出し、詩の現在に新たな回路を呈示する原理的模索、ついに結実なる。
目次
「旅上」の人・萩原朔太郎―方法としての境界
萩原朔太郎の短歌―「うた」の行方
萩原朔太郎と宮沢賢治―モナドロジーと身体/脱身体
高村光太郎と萩原朔太郎―方位としての生命/自然
伊東静雄の方法
初期伊東静雄の詩学―拾遺詩篇から
危険な抒情―『春のいそぎ』へ
「うた」論の行方
「うた」をめぐる中原中也論史
詩における「かたり」―中原中也へ太宰治から
「うた」と「かたり」の思想―続「詩における「かたり」」/太宰治と中原中也
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1
諸説あるが、『哀歌』を「私」と「半身」とのドッペルゲンガー説をかなり早い段階で提唱した静雄論を収録。要するに「己→汝(虚構)→己→汝(虚構)……」と簡明に静雄の原理を提出して見せた。これに影響を受けたのが杉本秀太郎の静雄論。ただ、この自己意識の堂々巡りは後の伊東静雄研究に絶大なインパクトを残したが、果たして、その自己循環的な円環的構造だけが『哀歌』の本質なのか、最近では疑問に思うこともある。例えば、「鶯」の「(私の魂)とは言えないが」「(私の魂)は記憶する」という矛盾はそれで解消できるのか。2023/11/04
-
- 洋書
- Yellow Fever